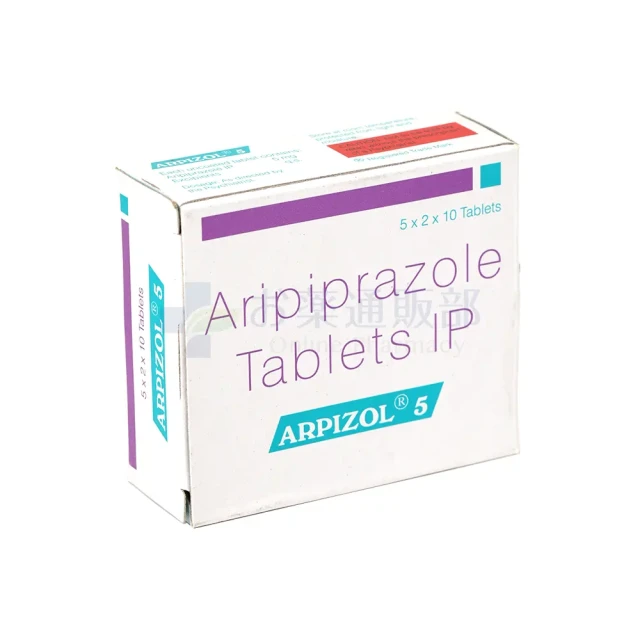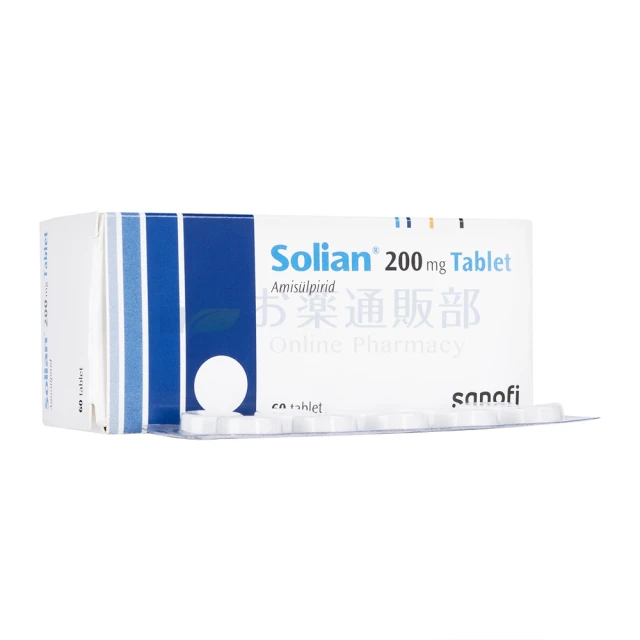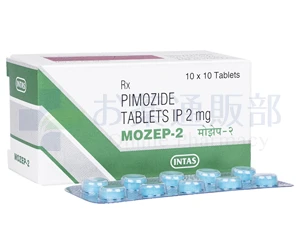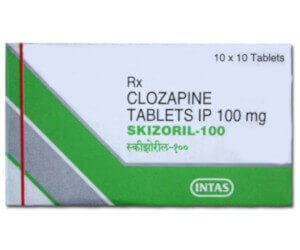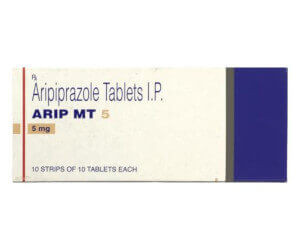統合失調症
統合失調症通販の商品一覧|エビリファイ・ドグマチールなど幻覚・意欲の低下の治療で有名な先発薬やジェネリック医薬品を数多くご紹介。安全なメーカー正規品のジェネリック医薬品や海外医薬品を最安値でのお求めは【お薬通販部】にお任せください!!
統合失調症人気ランキング
統合失調症の商品一覧
現在の検索条件
-
クロルプロマジン
3,480円
在庫ありクロルプロマジンは、DDファーマ社が開発した精神神経安定薬で、コントミンのジェネリック医薬品です。 ベゲタミンの名で日本でも知られているクロルプロマジン塩酸塩が成分として含まれています。 ドーパミンの過剰放出によって引き起こされる統合失調症の治療薬として開発された医薬品で、ドーパミンのD2受容体を阻害して過剰反応をおさえ直接作用して興奮や喪失感、不安感などを鎮めます。 感情の高ぶりを穏やかにして、吐き気の治療にも使用されています。 お薬通販部では、クロルプロマジン100mgの購入が可能となっています。 ※発送時期によりパッケージが異なる場合がございます。
-
アリピプラゾールMT
5,180円~
在庫ありアリピプラゾールMTは、トレントファーマ社が開発した非定型抗精神病薬で、エビリファイのジェネリック医薬品です。 脳内の神経伝達物質であるドパミンなどの受容体に作用し、幻覚・妄想などの症状を抑え、強い緊張や不安・うつ状態の精神状態を安定させていきます。 ドーパミンが過剰である場合は抑制し、不足している場合は活性化して増加させる作用をもった医薬品です。 お薬通販部では、アリピプラゾール5mg/15mgの購入が可能となっています。
統合失調症とは?幻聴や幻覚・極度の緊張などの症状に効く薬は?
ストレス社会の日本では精神疾患を抱えている人が非常に多く、中でも統合失調症は100人に1人が発症しているといわれています。
統合失調症になると、主に以下のような症状が現れます。
- 統合失調症の主な症状
-
- 幻聴
- 幻覚、妄想
- 感情表現、意欲の低下
- 記憶力、注意力の低下
- 不眠など
幻聴や幻覚は代表的な症状として挙げられます。幻覚や幻聴を放置していると日常生活に大きな影響を与えてしまうため、早めの治療がとても重要です。
今回は統合失調症の特徴や治療方法、幻聴や幻覚の症状改善に有効なおススメの治療薬をまとめて解説していきます。
統合失調症についてよくある質問
統合失調症がどのような病気なのかよくわからない方に向けて、まずはよくある質問をいくつか見てきましょう。
参考文献:こころの情報サイト「統合失調症」
統合失調症になりやすい人はどんな人ですか?
統合失調症を発症するはっきりとした原因は分かっていませんが、以下のいずれかに該当する方がなりやすいといわれています。
- 統合失調症になりやすい人
-
- ストレスを受けやすい方
- 内向的で人とのコミュニケーションが苦手な方
- 近親者に統合失調症の発症者がいる方
- 脳梗塞や脳出血など、脳に関連する病気の既往歴がある方
統合失調症の人の話し方や特徴はありますか?
以下のような話し方をする方や特徴を持つ方は、統合失調症を発症している恐れがあります。
- 統合失調症の人の特徴
-
- 話に一貫性がない
- 話の途中で早口になってくる
- 会話のキャッチボールが成立しにくい
- 独り言が極端に多い
- 幻覚や幻聴、妄想を基にした会話をする
- 突然笑ったり怒ったりする
もしこれらの症状が自分に当てはまる場合は統合失調症の恐れがありますので、早めに病院を受診した方が良いでしょう。
統合失調症の人にしてはいけないことは何ですか?
統合失調症は本人の治療も大事ですが周りのケアも非常に重要で、以下に挙げる間違った対応をしてしまうと症状の悪化を招いてしまいます。
- 統合失調症の人へのNG対応
-
- 相手の話を遮る
- 幻覚や幻聴、妄想を真っ向から否定する
- 相手を心配するなど
相手の気持ちを思いやって明るく寄り添うことが、統合失調症を治療する第一歩となるでしょう。
統合失調症は治療で治りますか?
統合失調症は薬物療法やリハビリテーションを実施することによって、幻覚や幻聴といった辛い症状を抑えることができます。
ただし、完治を目指すには数か月単位の長期治療が必須なので、気長に治療を続けなければいけません。
統合失調症の薬を飲むと幻聴は消えますか?
幻聴は統合失調症の主な症状の一つです。幻聴は日常生活の大きな障害となるため、一刻も早く治したいですよね?
幻聴の症状が現れる大きな要因として、脳内物質の一種であるドーパミンの過剰分泌が挙げられます。ドーパミンが増えると脳が興奮状態に陥り、幻覚や幻聴など現実には存在しない物や音が見えるようになってしまいます。
統合失調症の治療薬には、抗精神病薬と呼ばれるものがあります。抗精神病薬はドーパミンの過剰分泌を抑制する成分が含まれており、ドーパミンを正常な量に戻すことによって幻覚や幻聴の症状を抑えることができます。
抗精神病薬の服用はリハビリテーションより即効性に優れていますので、幻聴を早く消したい方は抗精神病薬の服用がおススメです。
統合失調症の症状からみる3つの病型は?
| アリピプラゾール | トフィソパム | スキゾリル | |
|---|---|---|---|
 |
 |
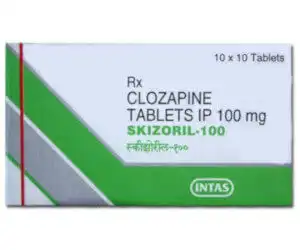 |
|
| 病型 | 破瓜型(解体型) | 緊張型 | 妄想型 |
| 有効成分 | アリピプラゾール | トフィソパム | クロザピン |
| 特徴 | アリピプラゾールはサンファーマが開発した非定型抗精神病薬で、エビリファイのジェネリック医薬品です。ドーパミンなどの受容体に作用して、幻覚・妄想などの陽性反応や強い緊張や感情の低下など陰性反応を安定させます。 | トフィソパムはコンサーンファーマが開発したベンゾジアゼピン系の抗不安薬で、グランダキシンのジェネリック医薬品です。自律神経系の緊張不均衡を是正し、発汗などの各種症状を改善します。 | スキゾリルはインタスファーマが開発した非定型抗精神病薬で、クロザリルのジェネリック医薬品です。治療抵抗性(効き目が確認できない)に効果があります。 |
| 価格 | 1錠 45円~ | 1錠 37円~ | 1錠 28円~ |
統合失調症は現れる症状によって、「破瓜型(解体型)」「緊張型」「妄想型」の3つの病型に大きく分けられます。
治療方法や使う薬もそれぞれ異なるため、自分がどの型なのか理解することによって、症状の早期改善を目指すことが可能です。
それぞれの特徴を、一つずつ詳しく見ていきましょう。
破瓜型(解体型)
解体型とも呼ばれる破瓜型の特徴は以下の通りです。
- 破瓜型(解体型)の特徴
-
- 感情の起伏が乏しくなる
- 思考がまとまらなくなる
- 無口、無関心になる
- 他人との接触を避けるようになる
- 症状が長く続きやすい
破瓜型は思春期から青年期の方が発症しやすい型で、統合失調症の症状の中でも陰性症状が主に現れます。
陽性症状と陰性症状については後で詳しく解説しますので、そちらを参考にしてください。
ドーパミンを抑える薬とは?
ドーパミンを抑える薬は抗精神病薬とも呼ばれ、脳内のドーパミン受容体を遮断してドーパミンの働きを抑制する効果を持っています。
ドーパミンは脳内物質の一種で、何らかの影響でドーパミンが過剰になると脳が興奮状態に陥ってしまいます。
脳が興奮状態になると幻覚や幻聴の症状が起きやすくなるため、ドーパミンを抑える薬は統合失調症の治療にとても有効です。
アリピプラゾール

アリピプラゾールは、サンファーマ社が開発した非定型抗精神病薬で、エビリファイのジェネリック医薬品です。
ドーパミンなどの受容体に作用し、幻覚・妄想などの陽性反応や、強い緊張や感情の低下など陰性反応を安定させていきます。
緊張型
緊張型の特徴は以下の通りです。
- 緊張型の特徴
-
- 落ち着きがなく動き回る
- 急に暴れだす(興奮)
- 話しかけても反応しない(昏迷)
- 一度発症すると再発しやすい
突発的な運動性障害を起こしやすく、さらに興奮と昏迷という正反対の症状を繰り返してしまいます。
極度の緊張に効く薬は市販で購入できるのか?
小林製薬のイララックや日本臓器製薬のアガラン錠など、市販でも緊張に効く薬はいくつか販売されています。
しかし、いずれも病院で処方される統合失調症の薬より効き目は弱いので、服用しても症状が改善しない恐れがあります。
統合失調症と診断された方は市販の薬で対処しようとせず、病院で治療薬を処方してもらうか個人輸入代行で統合失調症に適した治療薬を購入しましょう。
トフィソパム

トフィソパムはコンサーンファーマが開発したベンゾジアゼピン系の抗不安薬で、グランダキシンのジェネリック医薬品です。
自律神経系の緊張不均衡を是正し、発汗などの各種症状を改善します。
妄想型
妄想型の特徴は以下の通りです。
- 妄想型の特徴
-
- 幻覚や幻聴、妄想に悩まされる
- 思考が混乱しやすい
幻覚や幻聴の症状が多くみられるため、他の型より日常生活に与える影響は大きいのが特徴です。
緊張型や破瓜型と比較して薬が効きやすいので、比較的治療しやすい型といわれています。
幻聴を消す・幻覚や妄想に効く薬は?
幻聴や幻覚、妄想が起きる原因として、ストレスや不安などによるドーパミンの過剰分泌が挙げられます。そのため、ドーパミンの働きを抑える抗精神病薬は、幻聴や幻覚といった症状によく効きます。
抗精神病薬は市販では販売されていませんので、病院で処方してもらうか個人輸入代行を活用しましょう。
また、薬の服用で幻覚や幻聴の症状が治まっても、服用を止めると再発する可能性があります。服用を中止する際は自己判断ではなく、必ずかかりつけの医師と相談してください。
スキゾリル
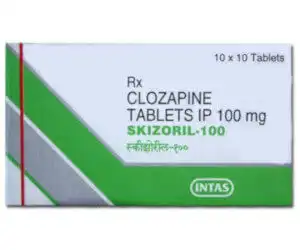
スキゾリルはインタスファーマが開発した非定型抗精神病薬で、クロザリルのジェネリック医薬品です。
治療抵抗性(効き目が確認できない)に効果があります。
陽性症状と陰性症状
統合失調症は陽性症状と陰性症状、2つの症状が現れます。それぞれの特徴を以下にまとめてみました。
| 陽性症状の特徴 | 陰性症状の特徴 |
|---|---|
| ・幻覚(特に幻聴)、妄想 ・誰かに支配されている感覚 ・考えがまとまらない ・極度の興奮 ・奇妙な行動 ・神経過敏など |
・感情の平板化 ・意欲の低下 ・思考能力の低下 ・自閉(引きこもり) ・倦怠感 ・抑うつなど |
陽性症状は「本来ないものが現れる(幻覚や幻聴)」ことが多く、ドーパミンの過剰分泌が原因といわれています。
陰性症状は「普段あるものがなくなる」ことが多く、ドーパミンの伝達低下が原因といわれています。
統合失調症の症状や病状経過
統合失調症は病気の進行具合によって4つの病期に分けることができ、病期ごとに現れる症状が異なります。
続いて、病期ごとの特徴を詳しく見ていきましょう。
前兆期
前兆期から急性期へ移行すると、幻覚や幻聴などの陽性症状が目立つようになります。周りから見た際、言動や行動がおかしくなるのが特徴として挙げられます。
発症頻度としては少ないですが、急性期でも意欲の低下や抑うつなどの陰性症状が現れることもあります。
幻覚や幻聴は日常生活に支障をきたす症状であるため、薬物療法やリハビリテーションによって早期改善を目指すことが重要です。
休息期
急性期の症状が治まってくると、次に訪れるのが休息期です。急性期特有の幻覚や幻聴などの症状は起こりにくいですが、倦怠感や意欲の低下など陰性症状が現れやすいです。
休息期はちょっとした刺激が原因で急性期に戻ることもあるため、休息期に入ったからといって安心してはいけません。
回復期
回復期は心身共に安定してきて、症状が回復してくる病期です。幻覚や幻聴、倦怠感や意欲の低下など陽性症状や陰性症状は起きにくくなります。
しかし、記憶力や注意力の低下、思考力の低下などの認知機能障害が現れることがあります。
また、症状が再発するケースもありますので、回復期に入っても安心しないようにしましょう。
統合失調症の治療方法や治し方は?
統合失調症は薬を服用する薬物療法と、精神科医によるリハビリテーションの2つがあります。
単独で行うケースと併用するケースがあり、病状に合わせて適切な治療方法を医師が選択します。それぞれどのような治療方法なのか、詳しく見ていきましょう。
薬物療法
薬物療法はドーパミンや脳内物質に関与する成分が有効成分として配合されており、比較的即効性に優れた特徴を持っています。
薬の分類としては抗精神病薬がメインで、症状に合わせて抗不安薬や睡眠薬などもよく使われています。
幻覚や幻聴、妄想による症状で悩まされている方は、薬物療法を実施するのが有効です。
薬物療法は薬への依存や薬を止めたときの離脱症状、副作用など服用する上で注意すべき点がいくつもあります。そのため、自己判断で薬物療法を開始するのは、非常にリスクが高いです。
リハビリテーション
リハビリテーションは精神科医が行う治療方法の一つで、神経認知機能及び社会認知機能のリハビリテーションがよく行われています。
| リハビリテーションの種類 | 主な治療効果 |
|---|---|
| 神経認知機能のリハビリテーション | ・患者のやる気を高める ・低下した思考能力の改善など |
| 社会認知機能のリハビリテーション | ・社会生活を送る上で必要な能力の改善 ・コミュニケーション能力の改善など |
薬物療法のような依存や副作用などはないため、安全性に優れた治療方法です。
しかし、幻覚や幻聴などの症状を、すぐに抑えるような効果は期待できません。リハビリテーションを行うには専門の知識が必要なので、一般の方が行うことはできません。
統合失調症の主な治療薬の一覧
幻覚や幻聴などの辛い症状を素早く鎮めたい方は、各種治療薬を服用するのがおススメです。
どの治療薬を服用すればいいのか分からない場合は、病院を受診して医師から教えてもらうのが安全かつ確実な方法です。
それぞれの治療薬の特徴を見ておきましょう。
抗精神病薬
抗精神病薬は統合失調症治療における中心的な治療薬として、病院でもよく処方されています。
抗精神病薬の特徴及び主な治療薬は以下の通りです。
リスコン

リスコンはリスパダールのジェネリック医薬品で、非定型抗精神病薬に分類される治療薬です。
幻覚や幻聴などの陽性症状だけでなく、意欲の低下や自閉などの陰性症状の改善にも効果を発揮します。リスコンは1錠当たりの価格も安く、経済的負担が気になる方におススメです。
アスプリト

アスプリトは、インタスファーマ社が開発した非定型抗精神病薬で、エビリファイのジェネリック医薬品です。
統合失調症の極度の緊張、興奮状態の陽性反応や無気力、感情の低下の陰性反応の両方に効果を発揮します。
シゾドン

シゾドンは、サンファーマが開発した非定型抗精神病薬で、リスパダールのジェネリック医薬品です。
ドーパミン不安定状態を整えて、陽性反応の妄想・幻覚・思考障害と陰性反応の自閉症・無関心・意欲の減退を改善し気分を安定させます。
抗不安薬
抗不安薬は精神安定剤とも呼ばれ、統合失調症による不安症状に対して優れた改善効果を持っています。
その他の特徴や主な治療薬は以下の通りです。
オーロリクス

オーロリクスは不安症状や気分の落ち込みを改善する効果を持っています。副作用や離脱症状が起きにくいなど、安全性に優れています。
オーロリクスは日本では承認されていない薬であるため、購入するためにはお薬通販部のような個人輸入代行を利用する必要があります。
パロキセチン

パロキセチンは選択的セロトニン再取り込み阻害薬 (SSRI)で、パキシルのジェネリック医薬品です。
気分の落ち込みによる思考の低下、行動、感情などを下向きから上向きに改善させていきます。
ジェイゾロフト

ジェイゾロフトは、ファイザーが製造・販売している選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)です。
薬物相互作用が出にくいとされ、うつ病・うつ状態、パニック障害、外傷後ストレス障害(PTSD)の改善に使用されています。
抗うつ剤
抗うつ剤は神経伝達物質の一種であるモノアミンを増やす作用によって、うつ症状を軽減することができます。
統合失調症による陰性症状はうつ症状に似ているため、抗うつ剤の服用で症状改善が図れます。特徴及び主な治療薬は以下の通りです。
ソリアン

ソリアンはドグマチールのジェネリック医薬品で、うつ病の改善に加えて統合失調症の陰性症状の改善にも期待できます。
また、服用量を調節することによって、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治療薬としてもご使用いただけます。
サインバルタ

サインバルタは、イーライリリーが開発したセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)です。
うつ病・うつ状態以外に糖尿病神経障害や各種疾患の疼痛の治療に使用されています。
イフェクサーXR

イフェクサーXRは、日本国内ではイフェクサーSRとして知られるセロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)です。
セロトニン、ノルアドレナリンの量を増やし、不安や気分の落ち込みと意欲・気力の低下を改善します。
シタロプラム

シタロプラムは選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)で、Celexaのジェネリック医薬品です。
セロトニンの量を増やすことで神経伝達を活性化し、うつ病・うつ状態、不安障害や月経前不快気分障害の症状を改善します。
睡眠薬
不眠や寝つきの悪さ、浅い眠りも症状として現れることがあります。これらの症状に悩まされている方は、睡眠薬の服用も症状改善に有効です。
睡眠薬の特徴と主な治療薬は以下の通りです。
ソクナイト
.jpg.webp)
ソクナイトはルネスタのジェネリック医薬品で、非ベンゾジアゼピン系に分類される睡眠薬です。薬の効果が翌朝まで残りにくく、依存性や耐性も生まれにくいといわれています。
とても使いやすく安全性も高いため、はじめて睡眠薬を服用する方にもおススメです。
フルナイト

フルナイトは、サンファーマ社が開発した不眠症治療薬で、ルネスタのジェネリック医薬品です。
入眠障害や中途覚醒にも効果があり、依存性が少なく翌日にも眠気を持ち越さない安全性の高い医薬品です。
ハイプロン

ハイプロンは非ベンゾジアゼピン系の睡眠薬で、ソナタ(sonata)のジェネリック医薬品です。
作用時間が短く、ベンゾジアゼピン系の睡眠薬と比べると依存性が低いのが特徴です。
抗精神病薬の副作用を抑える薬
抗精神病薬を服用した際、主に以下のような副作用を起こすことが報告されています。
- 主な副作用
-
- 錐体外路症状(EPS)
- 高プロラクチン血症
- 便秘、口喝
- ふらつき
- 眠気
- 体重増加など
これらの副作用を完全に防ぐことはできませんが、服用する薬の量を減量したり生活習慣を改善したりするのが一般的な対処法です。
また、錐体外路症状(EPS)に関しては、抗コリン薬の服用が有効といわれています。
| 錐体外路症状(EPS)とは? | 抗コリン薬の効果 |
|---|---|
| ・ドーパミンの過剰ブロックが原因 ・運動調節が上手くいかなくなる ・本人の意思と無関係に体が動く |
・筋肉の震えやこわばりの軽減 ・落ち着きのなさや動きたくなる衝動を抑える |
錐体外路症状(EPS)の症状を抑えるために抗コリン薬の服用を考えている方は、自己判断で服用を開始せずに必ず医師と相談してからにしましょう。
統合失調症の発症原因と考えられるケース
統合失調症は100人に1人が発症するといわれており、男女比に大きな差はなく10代後半から30代の方が多いです。
しかし、発症する原因は現在でもはっきりわかっていません。以下のような要因が発症原因として挙げられています。
- 発症の要因とされるもの
-
- 大きなストレス
- 両親からの遺伝
- 脳の病気
- 生まれつきの性格(控えめ、内向的など)
この中でも「大きなストレス」は回避できる要因であり、日常生活を送る上でストレスを受けない・溜めないようにすることは非常に大切です。
統合失調症の薬を飲まない方がいい人は?
統合失調症の治療において薬物療法は非常に有効ですが、すべての方に有効というわけではありません。
とくに、下記に該当する方は薬物療法を避ける必要があります。
- 薬物療法を避ける必要のある方
-
- 重篤な副作用を起こしたことのある方
- 薬物過敏症をお持ちの方
- 妊娠中または妊娠している可能性のある方
- 授乳中の方
- 過去に薬物に対して乱用や依存症を起こしたことのある方
いずれかに該当する方はリハビリテーションを中心に治療するか、かかりつけの医師と治療方針について相談した方がいいでしょう。
統合失調症の薬の口コミまとめ
統合失調症は誰もが発症する可能性のある、身近な精神疾患の一つです。きなり幻覚が見えたり幻聴が聞こえたりしてきたら、統合失調症を発症している恐れがあります。
早めの治療が重症化と治療の長期化を避ける重要なポイントなので、気になる症状が現れたら早めに精神科または心療内科を受診してみましょう。
クエチアピン
- いいクチコミ
-
ムーミン(59歳)
数年前から幻聴らしきものが聞こえながらも運転の仕事をしているため100mgを一錠だけ夜に服用して睡眠はしっかりと取っています。(睡眠薬としても効果あり) 幻聴は近隣に住むアパートからの嫌がらせの声の様に聞こえるのですが外へ出たら誰も居ない。自分を疑いながらも自宅借家に住んでいます。 とりあえず、外に出たら聞こえないので嫌がらせみたいな幻聴に耐えています。先では引っ越す予定です。
- 悪いクチコミ
-
ならはし(34歳)
妊娠中のため服用を中止していますが、飲みたくてしょうがないです。中毒性があるようです。子どものためにも飲みたくないですが、つらいです。
クロルプロマジン
- いいクチコミ
-
コスモス(47歳)
幻聴の症状のある息子に服用させていますが、服用している間は症状が落ち着いているようです。深刻な副作用もなさそうなのでこのまま使用して様子をみていきたいです。
- 悪いクチコミ
-
ハム子(26歳)
不安障害があるため服用し始めましたが効果はイマイチ…。量を調節しながら服用してみたいと思います。副作用はありませんでした。
スキゾリル
- いいクチコミ
-
あーさん(42歳)
統合失調症として診断されて、今まで様々な薬を試しましたがクロザリルジェネリックにしてから幻覚が良くなった気がします。価格も安いのでこちらを続けていきたいです。
- 悪いクチコミ
-
サイチェン(33歳)
安いのは良いんですが、私の症状にはあまり効果が感じられませんでした。もうちょっと飲み続けたら効果出てくるんですかね。もう少し試してみます。