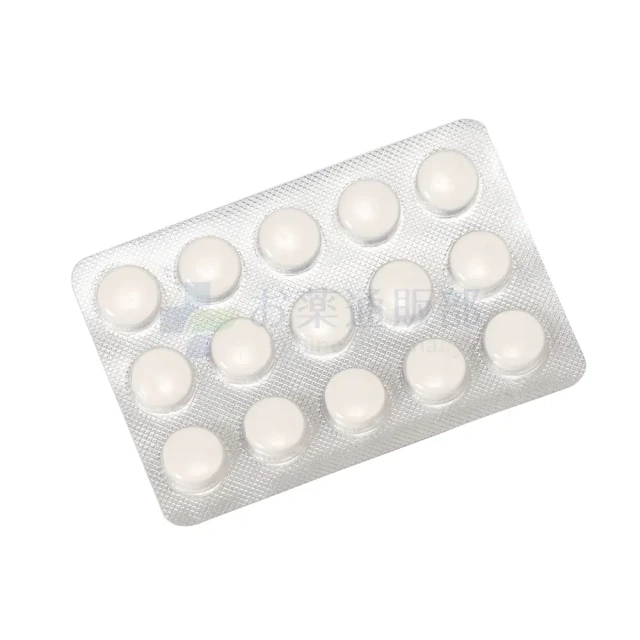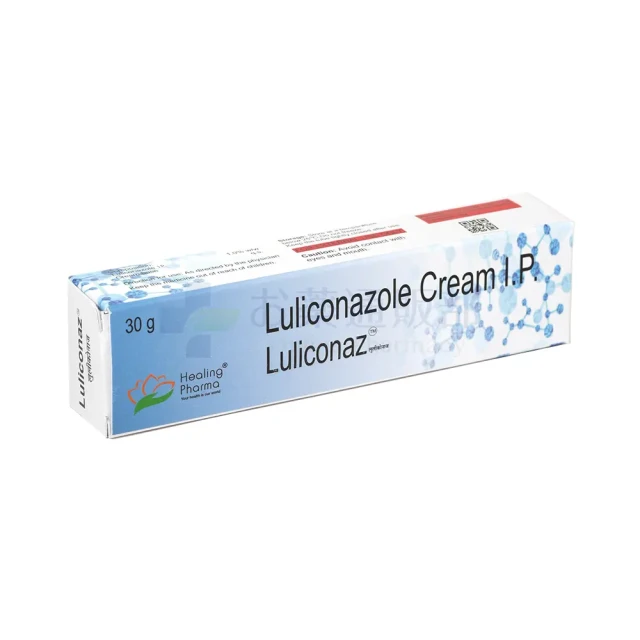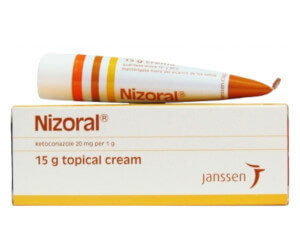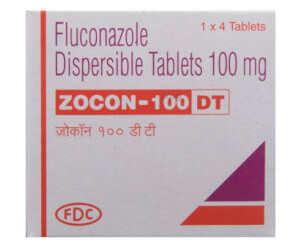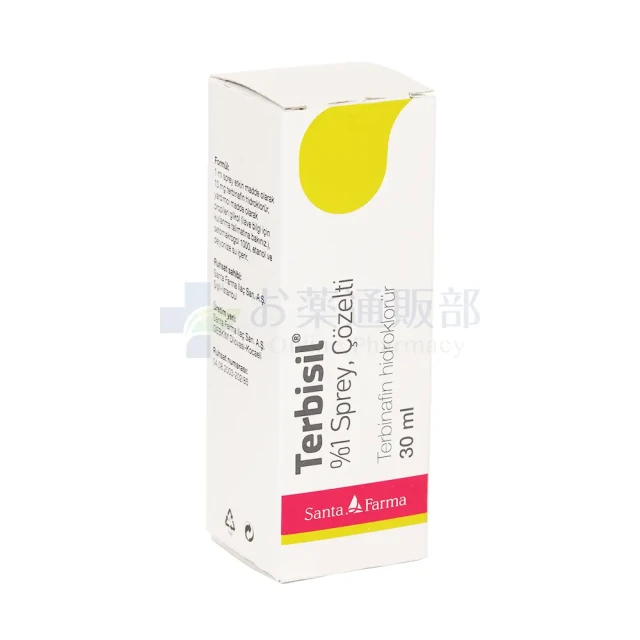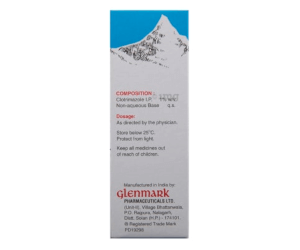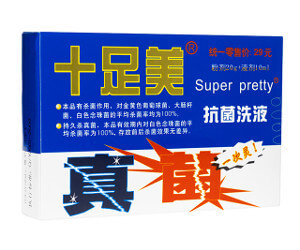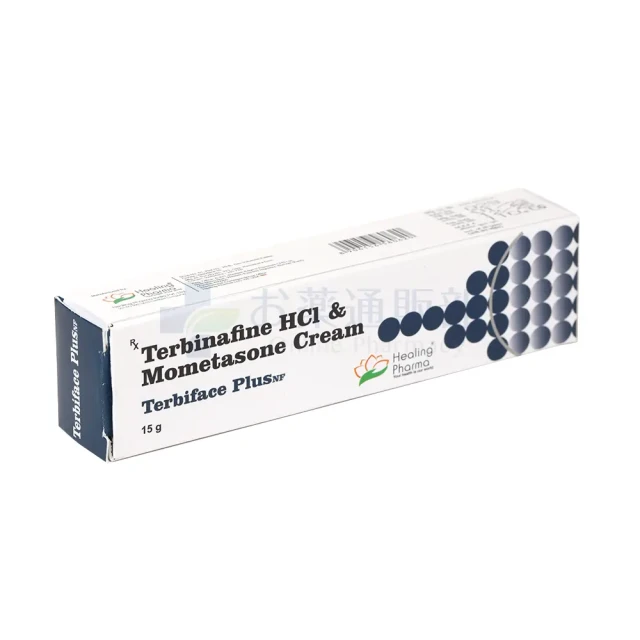水虫・いんきんたむし
水虫・いんきんたむし治療薬通販の商品一覧ページです。水虫・いんきんたむしなどの真菌の増殖を抑える効果がある治療薬を最安値でご紹介しています。
水虫・いんきんたむし人気ランキング
水虫・いんきんたむしの商品一覧
現在の検索条件
-
クロトリマゾールクリーム
2,080円~
在庫ありクロトリマゾールクリームは、グレンマークが開発した抗真菌薬です。 日本で処方されているエンペシドと同成分で、患部に直接塗るクリームタイプの医薬品となります。 主成分のクロトリマゾールは、真菌の増殖を抑制することで、カンジダ症、水虫、いんきんたむしなど多くの治療に効果が見込めます。 お薬通販部では、1%の購入が可能となっています。
-
クロトリマゾールローション
2,500円~
在庫ありクロトリマゾールローションは、インドのグレンマークが製造する抗真菌薬です。 真菌が原因で引き起こされる水虫・いんきんたむし・カンジダ症などの様々な皮膚の真菌感染症治療に用いられている薬剤になります。 患部の皮膚に直接塗布することで、真菌の成長や増殖を抑え、また殺菌させる作用があり、症状を改善させる効果があります。 お薬通販部では、1%の購入が可能となっています。
-
スポラノックス・ジェネリック(イトラノックス)
2,000円
在庫なしスポラノックス・ジェネリック(イトラノックス)は、性病のカンジダ症や白癬菌などに殺菌効果をもつ抗真菌薬です。病気の原因となる真菌の増殖を抑えることで、治療効果を発揮します。 日本ではイトリゾールと呼ばれるスポラノックスのジェネリックのため、安く購入できるのもメリットです。 内服薬のため、外用薬で効果がえられなかった場合でも、効果が期待できます。また、毎日塗布する手間もありません。 人間だけでなく、犬や猫の真菌症の治療にも用いられます。
-
トラボコートクリーム
2,860円~
在庫なしトラボコートクリームは皮膚に生えた真菌(カビ)を殺し、炎症を抑えます。 有効成分のジフルコルトロン吉草酸エステルと、イコナゾール硝酸塩が皮膚の赤みやかゆみをやわらげ、カビを殺菌して皮膚真菌症を治療する外用薬です。
-
マックダームK10クリーム
2,500円~
在庫ありマックダームK10クリームは、抗真菌薬ケトコナゾールのほか、フルオシノロンアセトニド、ネオマイシン、メンソールを配合した外用薬です。 直接皮膚に塗って使用し、水虫やカンジタ、いんきんたむしといった真菌が原因の疾患に特徴的な不快なかゆみや刺激感の改善効果があります。 マックダームK10クリームはインドの製薬会社ヒーリングファーマが製造・販売を行っています。
-
テルビフェイスプラスクリーム
2,960円~
在庫ありテルビフェイスプラスクリームは、ヒーリングファーマが販売する皮膚の真菌感染症に対する外用薬です。 このクリームは、抗真菌作用を持つ「テルビナフィン」と、抗炎症効果のある「モメタゾンフランカルボン酸エステル」を主成分としており、カンジダ症や白癬(水虫)、癜風など、さまざまな真菌感染症に対して効果を発揮します。 皮膚に直接塗布するタイプの薬で、効果的に症状を改善できます。
-
ラミシール・ジェネリック(テルビシップ)
2,500円~
在庫ありラミシール・ジェネリック(テルビシップ)は内服薬の抗真菌薬で、塗り薬では治りにくい爪の水虫やかかとの水虫の治療に適しています。日本の皮膚科でよく処方される「ラミシール」のジェネリックで、ラミシールと同じ有効成分「テルビナフィン」を含有しています。インドの大手製薬会社「シプラ社(Cipla)」が製造しています。 高温多湿な日本の気候では特に靴の中は水虫の原因となる白癬菌にとって最適な環境となりやすく、水虫に悩む方は多いです。テルビナフィンは特にこの白癬菌に対して強い殺菌力をもち、菌の発育を抑制して水虫を治療します。
水虫・いんきんたむしとは
いんきんたむしとは、「白癬(はくせん)」と呼ばれる病気の一種で、水虫の原因としても知られる白癬菌という真菌(カビ)が、陰嚢や内股の皮膚に寄生することで発症する皮膚真菌感染症です。
いんきんたむしは通称名で、医学的には「股部白癬(こぶはくせん)」と呼ばれており、正式な病名は「潜在性小水疱性斑状白癬」になります。
現在、いんきんたむしを含む白癬は多くの方が悩む感染症です。特に男性は一生に一度は、いんきんたむしの診断もしくは疑わしき症状がみられるともいわれています。
いんきんたむしの原因・症状・治療薬など正しい知識を身につけ、治療・予防に活かしていきましょう。
水虫・いんきんたむしの主な治療薬の効能と副作用
| ラミシール | クロトリマゾール クリーム |
テルビシル | ニゾラール | スポラル | ルリコナゾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 適応症状 | 皮膚カンジダ症、白癬など | 皮膚カンジダ症、白癬など | 皮膚カンジダ症、白癬など | 皮膚カンジダ症、白癬など | 皮膚カンジダ症、白癬など | カンジダ症、水虫など |
| 有効成分 | テルビナフィン | クロトリマゾール | テルビナフィン | ケトコナゾール | イトラコナゾール | ルリコナゾール |
| 特徴 | ラミシールはノバルティスが開発した抗真菌薬で、真菌の増殖を抑制し、カンジダ症や水虫など皮膚真菌症の治療に用いる経口服用タイプの医薬品です。 | クロトリマゾールクリームはグレンマークが開発した抗真菌薬で、真菌の増殖を抑制することで、カンジダ症、水虫、いんきんたむしなど多くの治療に効果があるクリームタイプの医薬品です。 | テルビシルはサンタファーマ社が開発した抗真菌薬で、皮膚真菌症の原因である真菌の発育を抑制し、カンジダ症や水虫などの症状を改善します。 | ニゾラールはインスタファーマ社が製造する経口タイプの抗真菌薬で、水虫やカンジダ症などのカビの一種である真菌が原因となって起こる幅広い症状に効果がある医薬品です。 | スポラルはヤンセン・シラグが製造する抗真菌薬で、真菌の成長や増殖を抑え、カンジダ症や水虫、いんきんたむし等に有効な医薬品です。 | ルリコナゾはヒーリングファーマが製造する抗真菌薬で、イミダゾール系に分類される、皮膚真菌症に広く用いられているクリームタイプの抗真菌剤です。 |
| 価格 | 1錠 126円~ | 1本 1,866円~ | 1本 1,686円~ | 1錠 128円~ | 1錠 337円~ | 1本 1,500円~ |
いんきんたむしを含む白癬の治療薬である抗真菌薬は、1960年代に一般的に用いられるようになって以来、開発・研究と抗真菌薬耐性菌との戦いを繰り返し今日に至っています。
現在では外用薬・内服薬とさまざまな種類の抗真菌薬が登場し、さまざまないんきんたむし治療薬の選択が可能になっていることに加え、医療用医薬品(処方薬)だけではなく一般用医薬品(市販薬)としても販売されており、誰でも手軽に購入することが可能です。
水虫やいんきんたむしの治療に使われる抗真菌薬として、ラミシール、クロトリマゾール、テルビシル、ニゾラール、スポラル、ルリコナゾが広く知られています。
これらの薬剤は、それぞれ異なる成分を含んでおり、それぞれの効果や副作用にも違いがあります。
ラミシール

ラミシールはスイスのノバルティスが開発した抗真菌薬です。真菌の増殖を抑制し、カンジダ症、水虫など皮膚真菌症の治療に用いる経口服用タイプの医薬品です。
ラミシールは、水虫やいんきんたむしといった真菌感染症の治療に有効な医薬品です。
クリーム、錠剤、スプレーの形態があり、特にクリームは感染部位に直接塗布することで、かゆみや赤みを軽減します。
一方、錠剤は体内から感染を抑えるため、広範囲や深部の真菌感染に適しています。
スプレーは使用が簡単で、手が届きにくい部位にも効果的です。
ただし、副作用としては、肝機能障害や味覚障害、皮膚の刺激感が報告されているため、使用時には注意が必要です。
クロトリマゾール

クロトリマゾールクリームは、グレンマークが開発した抗真菌薬です。日本で処方されているエンペシドと同成分で、患部に直接塗るクリームタイプの医薬品です。
クロトリマゾールは、イミダゾール系に分類される抗真菌成分名および、成分配合の医薬品名(海外製)です。
真菌の細胞膜生成を阻害する作用があり、細胞膜の機能を低下させることで真菌を死滅させる効果が期待できます。
クロトリマゾールは数あるイミダゾール系抗真菌薬の中で、世界で最初に開発された成分で、高い抗真菌作用と幅広い抗真菌スペクトルがあることから、白癬以外にもカンジダ症や癜風の治療薬としても用いられています。
また、外用剤としての使用では副作用のリスクが低いことから、医療用医薬品以外にも一般用医薬品としての販売も可能になっている医薬品成分です。
国内でのクロトリマゾール配合の抗真菌薬は、医療用医薬品では先発医薬品のエンぺシドクリーム、ジェネリック医薬品(後発品)のタオンゲル・タオンクリームで、一般用医薬品ではエンぺシドLクリーム・ピロエース・クロトリンゼリーなどがあります。
海外の商品も合わせると、最も種類が多い抗真菌薬で、軟膏剤・クリーム剤・液剤・ジェル剤・ローション剤とさまざまな剤形の商品が販売されており、使用しやすいものを選択できます。
主な副作用として、使用部位に発疹やかゆみ、赤みが見られることがあります。まれに、皮膚のひりひり感や炎症を感じる場合もあります。
テルビシル

テルビシルはサンタファーマ社が開発した抗真菌薬で、日本でも処方されているラミシールクリームのジェネリック医薬品です。有効成分テルビナフィンが皮膚真菌症の原因である真菌(カビ)の発育を抑制し、カンジダ症や水虫などの症状を改善します。
テルビシルは、アリルアミン系に分類される抗真菌成分テルビナフィンを有効成分とする医薬品です。
真菌細胞内の代謝酵素を選択的に阻害する作用があり、細胞膜の機能を低下させることで真菌を死滅させる効果が期待できます。
テルビナフィンは、高い抗真菌作用と幅広い抗真菌スペクトルがあることから、白癬以外にもカンジダ症や癜風にも適応があり、さらに真菌細胞内への移行性に優れていることから、白癬菌が角質深くまで寄生している深在性真菌症にも有効な成分です。
外用剤としての使用では副作用のリスクが低いことから、医療用医薬品以外にも一般用医薬品としての販売も可能になっている医薬品成分です。
医療用医薬品では内服剤も存在しています。
国内でのテルビナフィン配合の抗真菌薬は、医療用医薬品では先発医薬品のラミシールと多数のジェネリック医薬品があり、一般用医薬品ではラミシールDX・ダマリングランデ・エクシブなどがあります。
クリーム剤・液剤・スプレー剤・錠剤とさまざまな剤形の商品が販売されており、症状や塗布部位によって選択できます。
主な副作用としては、胃腸の不快感や味覚異常が報告されています。
また、発疹やかゆみなどの皮膚反応も見られることがあります。重い副作用としては、まれに肝機能障害が起こることもあります。
ニゾラール

ニゾラールクリームは、ヤンセンファーマが製造する抗真菌薬です。真菌が原因で引き起こされる水虫・いんきんたむし・カンジダ症などのさまざまな皮膚の真菌感染症治療に用いられている医薬品です。
ニゾラールは、イミダゾール系に分類される抗真菌成分ケトコナゾールを有効成分とする医薬品です。
真菌の細胞膜生成を阻害する作用があり、細胞膜の機能を低下させることで真菌を死滅させる効果が期待できます。
ケトコナゾールは、高い抗真菌作用と幅広い抗真菌スペクトルがあることから、白癬以外にもカンジダ症や癜風にも適応があり、さらに真菌細胞内への移行性に優れていることから、白癬菌が角質深くまで寄生している深在性真菌症にも有効な成分です。
外用剤としての使用での副作用リスクは低いですが、現在、一般用医薬品としての販売は認可されておらず、医療用医薬品のみでの販売となっています。
ケトコナゾール配合の抗真菌薬は、国内では医療用医薬品である先発医薬品のニゾラールと多数のジェネリック医薬品があり、クリーム剤・ローション剤・スプレー剤の商品が販売されています。
海外では医療用医薬品として外用剤に加えて内服用の錠剤も販売されており、またテストステロンの代謝酵素を阻害する働きもあり、脱毛症や脂漏性皮膚炎などにも効果が期待できることから、ケトコナゾールを少量含有するシャンプーや石鹸も市販されています。
主な副作用としては、使用部位の痒みや発疹、赤みが報告されています。まれに、皮膚がヒリヒリする感じや腫れが生じることがあります。
スポラル

スポラルは、ドイツの製薬会社ヤンセン・シラグが製造する抗真菌薬です。真菌(カビなど)が原因で引き起こされる真菌感染症に用いられる医薬品です。
スポラルは全身性の真菌感染症にも使用される強力な抗真菌薬です。
内服薬としても提供され、特に重症の感染に対して効果を示します。
ただし、スポラルを使用する際にはいくつかの副作用に留意する必要があります。
主な副作用としては、胃腸の不調、頭痛、発疹などが報告されており、まれに味覚障害や肝機能障害が起こることがあります。
ルリコナゾ

ルリコナゾは、インドの製薬会社ヒーリングファーマ社が製造する抗真菌薬です。日本でも処方されているルリコンクリームのジェネリック医薬品です。
ルリコナゾは、特に皮膚のカビ感染症を治療するために広く用いられており、感染部位に直接塗布することで、カビの成長を抑え、症状の緩和を図ります。
多くの患者が治療後、感染の軽減や完治を報告しています。
副作用に関しては、一般的には比較的軽微で、塗布部位における軽度の刺激感や赤み、かゆみが主です。
しかし、感じ方には個人差があり、まれに強い刺激感や皮膚のひび割れなどがあらわれることもあります。
白癬(はくせん)による病気
日本では原因真菌が同じであっても、白癬菌の感染部位・発症部位によって医学的な病名・一般的な呼び方が異なっているのが特徴で、症状や感染しやすい人も感染部位によって違いがあります。
また、白癬菌の種類は100以上あり、そのうち白癬の症状を引き起こすものだけでも40種類以上存在しています。
国内では、原因真菌としてトリコフィトン・ルブルム、トリコフィトン・メンタグロフィテスと呼ばれる白癬菌が最も多いものになりますが、それらも感染部位によって違いや差があります。
感染部位によって異なる白癬のそれぞれの特徴を紹介します。
いんきん
股部に白癬菌が寄生することで発症する皮膚疾患です。
医学的には「股部白癬」と呼ばれており、頑固な白癬菌という意味で「頑癬(がんせん)」と呼ばれることもあります。
発疹や赤みができ、強い痒みや痛みが生じるのが特徴で、股部に限らず大腿部・臀部と広範囲に広がることもあります。性器周辺の皮膚バリア機能を低下させてしまうこともあり、性感染症の要因になることもあります。
原因真菌は、トリコフィトン・ルブルムが最も多く、次いでトリコフィトン・メンタグロフィテスが多くなっています。
「いんきん」はいんきんたむしの略語として用いられることが多いですが、本来は股部付近の皮膚炎の総称であり、正確には「白癬菌が原因のいんきん=いんきんたむし」になります。
たむし
頭部・股部・手・足・爪以外の体部に白癬菌が寄生することで発症する皮膚疾患にです。医学的には「体部白癬」と呼ばれています。
発疹がでたり、赤くただれたりといったような状態になります。
部位によっては痒みを伴うこともありますが、多くは自覚症状がないのが特徴です。
首やワキは発症しやすい部位ですが、白癬菌が付着した箇所であれば、体のどこでも生じる可能性があります。
原因白癬菌は、トリコフィトン・ルブルムが最も多く、次いでトリコフィトン・メンタグロフィテスが多くなります。また、犬や猫に寄生することがあるミクロスポルム・カニスと呼ばれる動物好性菌が感染し発症することもあります。
医薬品などには「たむし」以外に「ぜにたむし」と表記されることもあります。
水虫
足に白癬菌が寄生することで発症する皮膚疾患です。医学的には「足白癬」と呼ばれています。
赤くなったり皮がむけたり角質が厚くなったりします。
夏から秋にかけて靴内の湿気が高まる季節に痒くなることがありますが、基本的に痒みが生じることは少なく、水虫であることに気づかない場合も多くあります。
指の間や足の裏に発症しやすくなります。
原因白癬菌は、年齢層や環境によって偏りがあり、高齢者の場合はトリコフィトン・ルブルムとなることが多く、若年者の場合はトリコフィトン・メンタグロフィテスが多くなります。
また、近年では柔道やレスリングなどの格闘技競技者の間でトリコフィトン・トンスランスと呼ばれる新型白癬菌の感染も増えてきており、体部白癬や股部白癬へ移行する事例も増えてきています。
爪水虫
爪に白癬菌が寄生することで発症する皮膚疾患です。医学的には「爪白癬」と呼ばれています。
爪が厚くなったり、白く濁ったりといったような状態になります。また、爪の成長がアンバランスになり、爪の変形の原因にもなるので、巻き爪や陥入爪を引き起こす場合もあります。
主に足の爪(特に親指)にみられることが多いですが、手の爪にも見られることもあります。
部位が爪なので痒みはありませんが、爪水虫は、水虫も併発していることが多く、この場合痒みを生じることもあります。
原因白癬菌は、トリコフィトン・ルブルムの場合がほとんどで、それ以外の白癬菌が原因となることはほとんどありません。
しらくも
頭部に白癬菌が寄生することで発症する皮膚疾患です。医学的には「頭部白癬」と呼ばれており、特に症状がひどいものは「ケルズス禿瘡(とくそう)」と呼ばれています。
大量のフケがでたり、頭皮が赤くなったり、髪の毛が細くなり弱くなったりします。
頭部白癬では痒みを生じることは稀ですが、ケルズス禿瘡になれば痒み・痛みを伴うこともあり、頭皮の炎症で脱毛症の原因にもなります。
頭皮・髪の毛と頭部全体にみられます。
原因白癬菌は、犬や猫に寄生するミクロスポルム・カニスや、牛に寄生するトリコフィトン・ベルコースムとなる割合が高いため、ペット飼育者や酪農家に多くみられる疾患です。
トリコフィトン・ルブルムやトリコフィトン・メンタグロフィテスでも感染することもありますが、近年では稀な症例です。
参考⽂献:日本皮膚科学会「白線(水虫・たむしなど)
いんきんたむしの原因
いんきんたむしは白癬菌が股部に付着し寄生することで発症します。
白癬菌は環境中のあらゆる物や場所に存在しており、環境中にある白癬菌が付着している物や人への接触によるもの、もしくは水虫など他の感染部位からの広がりによるものが感染の原因になります。
しかし、白癬菌はヒトの皮膚にも存在している常在菌であるため、少し付着しただけでは免疫機能が働くため、皮膚に異常が生じることはありません。大量に付着し、増殖した場合に角質層へと侵入し発症することになります。
感染・発症しやすい体質、しにくい体質は特にありませんが、高齢者や糖尿病患者、外用ステロイド剤を使用している方は、身体の免疫機能が低下していることもあり、発症しやすくなります。
白癬菌は、温暖な室内環境を好んで繁殖する性質を持っています。湿度70%・温度15度以上で活発に増殖するとされており、汗で蒸れやすい部位に特に発生しやすくなります。
常に皮膚を清潔に保ち、通気性を良くし、乾燥を防ぐなど、白癬菌が増殖しないようにすることが感染予防に最も大切です。
いんきんたむしの症状
症状は、陰部・股部に限らず、大腿部・臀部と広範囲にみられることもあります。 小さな発疹・紅斑から始まり、白癬菌の増殖や感染部位の拡大により、円状・楕円状・環状といった形状の大きな発疹・赤みになっていきます。
進行具合によってもさまざまですが、輪郭が特に赤く輪郭の内側は治っているように見える堤防上の発疹が、白癬菌感染の特徴になります。
乾燥すると、皮膚がひび割れたり、皮が剥がれ落ちたり、粉を拭いたような状態になり、気温や湿度などにより外見が変わることがあります。
さらに、治療を怠り症状が長引くと、皮膚の変色、または色素沈着を起こすこともあり、黒く跡が残ってしまう場合もあります。
痒みは初期から現れ始めます。症状が進行し悪化すると、強い痒み、または痛みが生じることもあります。夏場・入浴・睡眠時は皮膚の温度が高くなり、白癬菌の活性・増殖に好条件であるため、特に痒みが増す恐れがあります。
また掻くことは、皮膚が傷つき出血や化膿を引き起こすだけではなく、指や体部への感染拡大、傷口から白癬菌が侵入し血液や内臓への感染、と症状を悪化させる原因にもなります。
いんきんたむしの感染経路
白癬菌は、屋内外とはず空気中やあらゆる物に付着しており、特に温度や湿度が高い場所、湿っている物は白癬菌が増殖しやすい環境であるため要注意です。
また、白癬菌の種類によって、生息している環境が異なるため、それぞれの白癬菌の感染経路に注意が必要になります。
トリコフィトン・ルブルムやトリコフィトン・メンタグロフィテスは、国内のいんきんたむしの原因菌として最も多い白癬菌であり、生活上使用するあらゆる場所や物に付着している可能性があります。
温泉施設のイス・温水プール・公共施設のトイレの便座は、不特定多数の人が使用しており、直接股部が接触することもあり、特に感染の危険が高くなります。
トリコフィトン・トンスランスは、元々は海外で広がった白癬菌ですが、近年では国内での感染が報告されており、特に柔道やレスリングなどによる皮膚接触や床から感染することが多いとされています。
たむし(体部白癬)や水虫から発症し、いんきんたむしに移行する症例が多数あります。
特にミクロスポルム・カニスは、犬や猫などのペットに寄生している白癬菌で、ペットの飼い主への感染が多く、たむし(体部白癬)から発症し、いんきんたむしに移行する場合が多くなります。
いんきんたむしの治し方
| ルリコナゾ | クロトリマゾール クリーム |
テルビシル スプレー |
ラミシール・ ジェネリック (テルビシップ) |
|
|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
|
| 治療タイプ | 塗り薬 | 塗り薬 | スプレー | 服用 |
| 有効成分 | ルリコナゾール | クロトリマゾール | テルビナフィン | テルビナフィン |
| 特徴 | ルリコナゾはヒーリングファーマが製造する抗真菌薬で、イミダゾール系に分類される、皮膚真菌症に広く用いられているクリームタイプの抗真菌剤です。 | クロトリマゾールクリームはグレンマークが開発した抗真菌薬で、真菌の増殖を抑制することで、カンジダ症、水虫、いんきんたむしなど多くの治療に効果があるクリームタイプの医薬品です。 | テルビシルスプレーはサンタ・ファーマが製造・販売する抗真菌薬で、水虫・いんきんたむし・カンジダ症などの真菌感染症治療に用いられている外用スプレーの医薬品です。 | ラミシール・ジェネリック(テルビシップ)はシプラ社が製造している抗真菌薬で、内服薬なので塗り薬では治りにくい爪の水虫やかかとの水虫の治療に適しています。 |
| 価格 | 1本 1,500円~ | 1本 1,866円~ | 1本 1,700円~ | 1錠 68円~ |
いんきんたむしを含め白癬の治療は、痒みや発疹といった症状を抑えることはもちろんですが、最も重要なのは、患部に寄生する原因菌である白癬菌の増殖を抑え殺菌することにあります。
たとえ症状が治まっていても、白癬菌が少しでも残っていれば、それは完治とはいえません。
治療方法にはさまざまな選択肢がありますが、症状に合わせて正しい治療方法を選択することが、素早い完治に繋がるとともに、再発や知らないうちに感染拡大を防ぐことにもなります。
感染・発症後にとる治療方法・対処方法について、その概要やメリット・デメリットなど特徴を解説していきましょう。
- いんきんたむしの治し方
-
- 抗真菌薬で治療する
- 局所の清潔を保つ
抗真菌薬で治療する
いんきんたむしの原因である白癬菌の増殖を防ぎ、殺菌効果のある抗真菌薬を使用する治療方法です。
医療機関を受診し、いんきんたむしと診断された場合は、必ずといっていいほど抗真菌薬が処方されることもあり、いんきんたむし治療において主流であり優先される方法です。
最も効果的であることに加えて、現在ではさまざまな種類の抗真菌薬が、医療用医薬品だけではなく一般用医薬品(市販薬)としても販売されているため、誰でも手軽におこなえる治療方法といえます。
抗真菌薬は外用薬と内服薬(医療用医薬品のみ)が存在しますが、皮膚疾患であるため外用剤での治療が基本です。
しかし、広範囲または皮膚の深くまで感染しているなど症状がひどい場合は、医師の処方により、外用剤に加えて内服の抗真菌薬を服用することもあります。
1週間~10日ほど使用を継続すれば、症状が目に見えて緩和してきますが、角質奥深くまで白癬菌が感染している恐れもあり、また再発を防止するために、その後1~3ヶ月の使用継続が推進されています。
医薬品成分であるため、薬剤の選択や使用方法を誤ると悪化や副作用のリスクがあるため、注意が必要な方法でもあります。
局所の清潔を保つ
股部を清潔に保つことで白癬菌の増殖を防ぐ方法です。
不潔にしていると皮膚のバリア機能が低下し、また湿気の高い状態は白癬菌の増殖に好条件な環境であるため、いんきんたむしの発症リスクが高まってしまいます。
白癬菌は皮膚表面に付着してもすぐには感染せず、皮膚を清潔に保っていれば増殖することもなく発症することもありません。
具体的な例としては、風呂時は念入りに局所を洗う・運動後などの後は必ず汗を拭き取り除菌シートなどで身体を拭く・衣類は通気性の良いものを心がける・夏場はこまめに着替えるなどが効果的です。
また、こまめに手洗いをする・入浴後のタオルの使い回しを避けるなど、感染源を減らすことも重要です。
しかし、あくまでも予防や悪化防止にのみ有効であり、治療としての効果は低いものになります。
清潔に保つのみの対応では、症状が軽度の場合は自然治癒することもありますが、白癬菌の増殖や症状の進行が進んでいる場合は難しいのが現状です。
また、洗いすぎは角質に傷がつき、菌が侵入しやすくなってしまうため、注意も必要になります。
水虫・いんきんたむし治療薬を使用する際の注意点
水虫・いんきんたむしの治療薬を使用する際にはいくつかの重要な注意点があります。
- 水虫・いんきんたむし治療薬を使用する際の注意点
-
- 飲み合わせ
- 外用薬で効果がなければ内用薬も併用する
- 良くなっても最後まで治療薬を使い切る
飲み合わせ
水虫・いんきんたむしの治療に使用する内服薬は、他の薬との飲み合わせに注意が必要です。
例えば、イトラコナゾールやテルビナフィンなどの抗真菌薬は、一部の心臓病用薬や抗ヒスタミン薬と併用すると副作用が強まる可能性があります。
持病で何らかの薬を飲んでいる方は、かかりつけ医に相談し、安全な飲み合わせを確認しましょう。
外用薬で効果がなければ内用薬も併用する
外用薬だけでは効果が不十分な場合、内用薬の併用が推奨されることがあります。
外用薬は感染部位に直接作用しますが、重症や広範囲にわたる感染には内用薬が効果的です。
良くなっても最後まで治療薬を使い切る
症状が改善しても、最後まで治療薬を使用し続けることが重要です。
通常、いんきんたむしの治療期間は2週間から4週間ですが、これは感染の深刻さや範囲によって異なる場合があります。
治療薬を早期に中止すると、感染が再発したり、抗真菌薬に耐性を持つ真菌が発生するリスクがあります。
いんきんたむし治療薬の入手方法
いんきんたむしの治療薬である抗真菌薬は、元々は医師の処方が必要な医療用医薬品としてのみ販売されていたものです。
使用実績がある・副作用の心配が少ないといった条件を満たした医薬品成分が、次々と一般用医薬品(市販薬)として販売されるようになりました。
医療機関でしか購入できなかったものが、ドラッグストアや通販を利用して購入できるようになり、個人の判断で治療・薬剤・購入方法を選択する時代になってきています。
治療薬購入方法を紹介し、それぞれで入手できる医薬品の種類、方法のメリット・デメリットを解説していきましょう。
国内処方してもらう
病院やクリニックなど専門の医療機関を受診し、医師に処方してもらう方法です。
購入できる医薬品は、医療用医薬品のみで、一般用医薬品が処方されることはありません。
メリットは、診察や検査をおこない症状の度合いや原因菌が明確になるので、的確な治療を受けられるという点で、最も効果的な医薬品を専門家に選択してもらい、薬剤の使用方法や注意事項などを指導・説明してもらうことが可能です。
医療用医薬品は一般用医薬品と比較すると、同じ成分であっても多く配合されているため、効果は高いものになっています。
皮膚深くまで感染している・広範囲に感染している場合に服用することがある内服の抗真菌薬は、現在医療用医薬品でしか存在していません。
いんきんたむしを含む白癬の治療は、保険適応の対象になります。
デメリットは、医療機関に受診しなければならないこと、診察料・再診料・処方料などが発生しまうことがあり、市販の薬を購入するよりも時間も費用もかかることになります。
相手が医師であっても陰部を他人に見せることになるので、恥ずかしいといった理由で受診しないケースも多くあります。
市販薬を探す
薬局・ドラッグストアで、店頭に並んでいる市販の抗真菌薬を購入する方法です。
購入できる医薬品は、一般用医薬品のみで、医療用医薬品は購入することはできません。
メリットは、多くの種類の医薬品が販売されており、ほとんどが薬剤師不在でも購入できる第一類医薬品以外であるため、どのドラッグストアでも購入することが可能です。
医療機関に受診する必要がないので時間も費用も抑えられることもあります。
いんきんたむしで受診するのは恥ずかしいといった意見もあるため、市販薬の需要は非常に高くなっています。
デメリットは、自分の判断で医薬品を選択しなければならないことです。
症状の原因が白癬菌であるかどうかは検査で判明することでもあり、白癬菌の中には一部の抗真菌薬に耐性を持っているものもあることから、選択した抗真菌薬が無意味になる場合もあります。
また、一般用医薬品は医療用医薬品と比較すると、同じ成分であっても安全性を考慮して配合量が少ないことが多く、軽度~中度では治療可能ですが、中度以上では効果が不十分となる場合があります。
通販購入する
Amazonや楽天など大手通販サイト・医薬品メーカーの通販サイト・海外通販サイトを利用して抗真菌薬を購入する方法です。
購入できる医薬品は、国内の通販を利用した場合は一般用医薬品のみ、海外の通販を利用した場合は、海外の一般用医薬品に加えて医療用医薬品も購入できます。
メリットは、多くの種類の医薬品が販売されており、店頭に販売されていない商品も購入できること、医療機関に受診する必要がないので時間も費用も抑えられることがあります。
また、海外通販の場合は、国内では医師の処方が必要な医療用医薬品が手軽に購入できることもあります。いんきんたむしで受診したり店頭購入したりするのが恥ずかしいといった意見もあるため、通販購入は非常に需要が高くなっています。
デメリットは、医師の診察・検査を受けずに独自の判断で薬剤を選択し使用するので、効果的に治療できない場合もあることです。
白癬菌の中には一部の抗真菌薬に耐性を持っているものもあることから、選択した抗真菌薬が無意味になる場合もあります。
海外通販で購入できる医療用医薬品は、一般用医薬品に比べて効果が高い反面リスクも高くなっているので、治療中の病気・併用薬に注意しなければ、副作用や症状悪化の原因にもなる恐れもあります。
いんきんたむし(白癬)まとめ
いんきんたむしは、痒みや炎症の症状にとどまらず、悪化すると範囲の拡大、他部への移行、皮膚の色素沈着、皮膚のバリア機能低下による感染症リスクの増大などの恐れがあり、侮れない病気です。
しかし、しっかりと予防すれば感染することはなく、現在はさまざまな種類・効果の高い治療薬が開発されているため、適切な治療をすればほとんどが完治する病気でもあります。
いんきんたむしの原因や対処法、治療薬有効成分の作用や注意事項、商品の配合成分や口コミなど正しい情報や知識をしっかりともって、予防・治療するように心がけましょう。
水虫・いんきんたむし薬の⼝コミは︖
水虫・いんきんたむし薬を実際に使用されたレビューや口コミを紹介します。
水虫・いんきんたむし薬を後乳を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
クロトリマゾールクリーム
- いいクチコミ
-
くっきー (44歳)
薬局の薬よりも、断然水虫に効きました!コスパもいいです!いままで悩まされてきたのはなんだったのか…スマホですぐに買えるのもラクでいいですね。これからは常備します!
- 悪いクチコミ
-
おおしま (38歳)
カンジダ症に効くと妹から勧められて使い始めたけど、全然効果が無かった。妹は塗り始めてすぐに改善できたと言っていたのでかなり期待していたけど、体質の問題なのか塗り始めて2週間弱経った今でも膣周辺に痒みが残っています。
ニゾラールクリーム
- いいクチコミ
-
たいよう (34歳)
水虫の症状がひどいときに使っています。市販薬は効果がないため、病院に行っていましたが、これなら通販で簡単に購入できるため、とても助かっています。効果も副作用なども、病院で処方してもらう薬との差はありません。またリピートします。
- 悪いクチコミ
-
若乙女 (29歳)
カンジダ症に悩んでいたら友人から紹介されたので使ってみました。聞いていた話より全然効果が無かったです。友人は塗り始めてから1週間経たないうちに症状が改善したと言っていたけど、私は1週間過ぎてもまだ痒みが残っています。
テルビシル
- いいクチコミ
-
iida (38歳)
水虫ですが、これを塗ると症状が緩和されます。市販薬では効果がほとんどないので、とても助かります。普通の通販みたいに買えるのもいいですね。これからは常備しておこうとおもいます!
- 悪いクチコミ
-
いちご (38歳)
ラミシールクリームのジェネリック医薬品ということで、安心して使ったらまさかの副作用が現れてしまいました。これを塗った後に、必ず塗った場所で刺激感を感じてしまいます。副作用以外原因が考えられません。ラミシールクリームでは起きなかったのに…。