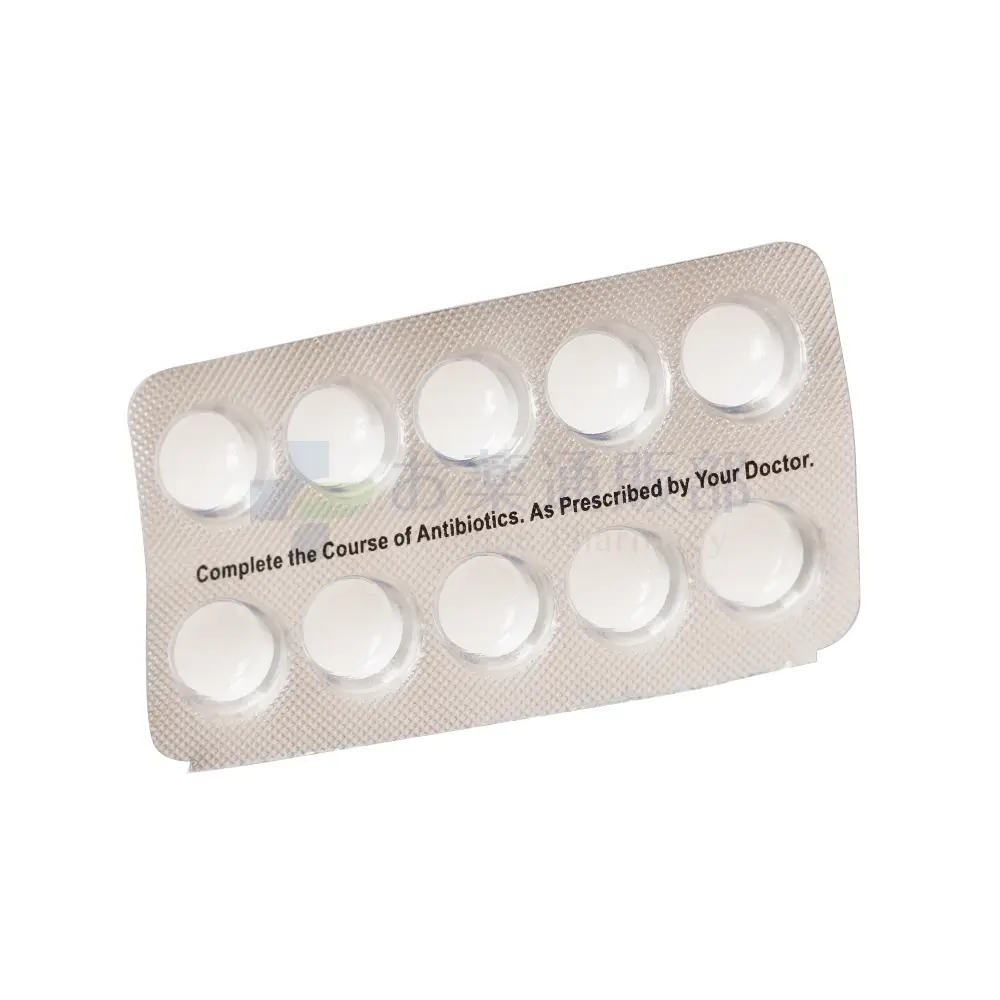アジーの有効成分、アジスロマイシンはどんな作用で病気を治す?体内ではこんなことが起きています!
アジーの有効成分であるアジスロマイシンは抗生物質であり、クラミジアや淋菌のような細菌感染症の治療に効果的です。 アジスロマイシンが細菌やヒトの体内に与える作用について解説します。

抗生物質の登場は多くの命が救われる、人類における偉大な発明となりました。
アジスロマイシンは、多様な細菌に有効な抗生物質でありながら、他のお薬と併用しても副作用が現れにくく、医療現場でよく利用されています。
この記事では、アジスロマイシンによる細菌治療の作用メカニズムや、体内における反応について解説します。
アジスロマイシンの特徴

アジーはアジスロマイシンという抗生物質を有効成分とするお薬です。
ここではアジスロマイシンが細菌を治療するメカニズムと、ほかの抗生物質と比較したアジスロマイシンの特徴についてご説明します。
アジスロマイシンのメカニズム
アジスロマイシンはタンパク質の作成を妨げることで細菌を治療するお薬です。
すべての生き物は生きるためにタンパク質を必要とします。
細菌も人間も、細胞の中にはリボソームという組織が存在し、リボソームは読み取った遺伝子情報をもとにタンパク質を作り出します。
アジスロマイシンは細菌のリボソームと結合することでリボソームの働きを無効化し、タンパク質の合成を妨げることで細菌の増殖を抑制します。
それとは対照的に、ヒトの細胞には細胞壁がないため抗生物質の影響を受けません。
抗生物質は細菌にのみ作用するので安全です。
アジスロマイシンと他の抗生物質の違い
抗生物質は静菌性と殺菌性の2つに分類されます。
このうち細胞の増殖を防ぐことで治療をするアジスロマイシンは、静菌性に当てはまります。
対照的に殺菌性の抗生物質は、細胞壁を壊して細菌を死滅させるお薬で、 例としてはペニシリンが有名です。
またマクロライド系という種類の抗生物質であるアジスロマイシンは、ペニシリン系の抗生物質と化学的性質が大きく異なるため、ペニシリンにアレルギーがある人でも服用可能なところがアジスロマイシンの強みだといえます。
アジスロマイシンの体内での作用
ヒトの体にとって、お薬は本来異物です。
このため人体にはお薬を排除しようと体外へと排泄する、代謝という仕組みが備わっています。
代謝の仕組みはシトクロムP450(CYP)と呼ばれる酵素が担っており、お薬の種類によってCYPの作用は変化する場合があります。
その一例として、アジスロマイシンと同じマクロライド系の抗生物質にエリスロマイシンがあります。
エリスロマイシンが阻害する酵素によって代謝される不眠症治療薬のベルソムラを併用すると、ベルソムラが代謝されず効果が強まるため、併用禁忌となっています。
アジスロマイシンは、大部分がCYPによる代謝を受けず未変化体として存在し、大半が未変化体のまま胆汁として排泄されます。
そのためアジスロマイシンは、ほかのお薬との相互作用による副作用のリスクが低い特徴があります。
胆汁として排泄されたアジスロマイシンは、主に便として体外に放出されます。
アジスロマイシンの構造
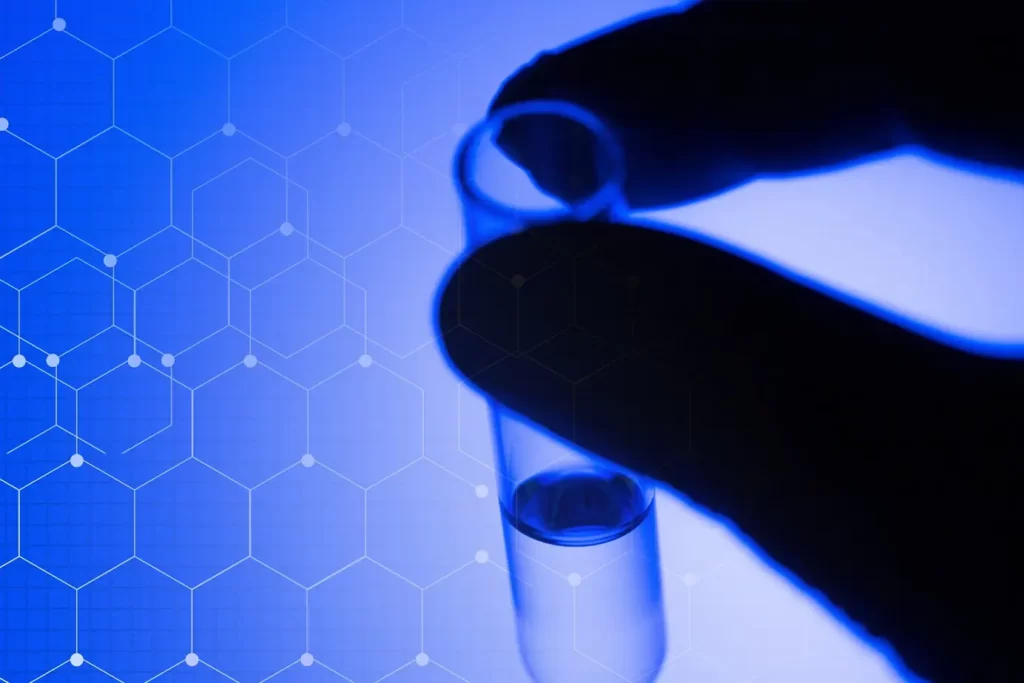
アジスロマイシンは、化学式C38H72N2O12で示され、水和物として服用するお薬です。
天然に存在したエリスロマイシンから作製した抗生物質であり、ラクトン環という共通の化学的構造を持ちます。
ラクトン環はマクロライド系抗生物質に共通する構造で、ケトライド系抗生物質にも存在します。
化学的構造の類似性から、マクロライド系やケトライド系のお薬で過敏症の症状が現われたことがある場合は、アジスロマイシンで副作用を起こすリスクが高まります。
マクロライド系やケトライド系の抗生物質に過敏症がある場合は、アジスロマイシンの服用時に注意が必要です。
まとめ

アジスロマイシンは、細菌のタンパク質の合成を妨げることで細菌の増殖を防ぎ、治療するお薬です。
併用による相互作用や副作用が少なく、安心して服用することができます。