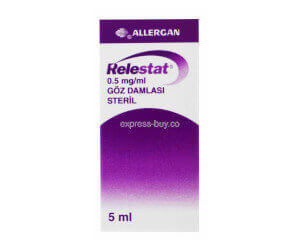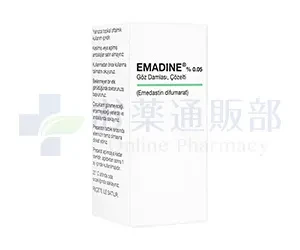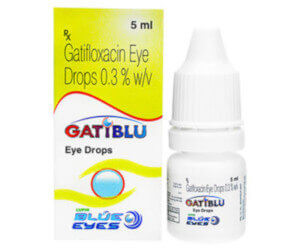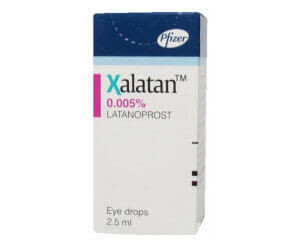眼病
眼病治療薬通販購入の一覧ページです。緑内障・白内障・ものもらい・結膜炎・細菌感染などに有効な目薬を最安値でご紹介しています。
眼病人気ランキング
眼病の商品一覧
現在の検索条件
-
シプロフロキサシン点眼薬
1,180円~
在庫ありシプロフロキサシン点眼薬は、シプラ社が製造しているニューキロノン系抗生物質のシプロフロキサシンを主成分とした点眼薬です。 細菌性の結膜炎や麦粒腫(ものもらい)などの治療に用いられます。 ニューキロノン系抗生物質は抗菌スペクトル(殺菌できる病原菌の種類の幅)が広い抗菌剤です。 したがって細菌性の眼病が疑われる時は第一選択肢として選ばれることが多い点眼薬です。 お薬通販部では、0.3%の購入が可能となっています。
-
ドルゾックスT点眼薬
2,810円~
在庫ありドルゾックスT点眼薬は、シプラ社が販売している点眼薬です。 緑内障や高眼圧症の治療に用いられています。 有効成分としてドルゾラミドとチモロールが含まれており、眼圧を下げる働きをします。 疲れ目の方は、目の筋肉が硬くなり一時的に眼圧が上がってしまうことがありますが、緑内障とは別のものです。 眼圧が高い状態が続くと視神経を圧迫し、視野が狭くなるほかに頭痛などの症状が出ることもありますので、お薬で上手に治療しましょう。 お薬通販部では、ドルゾラミド2%/チモロール0.5%の購入が可能となっています。
-
シプロフロキサシン眼軟膏
1,300円~
在庫なしシプロフロキサシン眼軟膏は、インドが本拠地であるFDC(エフ・ディー・シー)が製造・販売している眼科用の軟膏抗菌剤です。 シプロフロキサシン眼軟膏は、細菌やウイルスが原因の病気などに用います。 殺菌することで、感染症を治療し感染を防ぐことができます。 シプロフロキサシン眼軟膏の有効成分シプロフロキサシンは、細菌の増殖を抑制し、細菌性の結膜炎、ものもらい、眼瞼炎を治療します。 シプロフロキサシンは、様々な細菌に対して効果があるため、人間だけでなく、犬や猫にも使用できます。 お薬通販部では、1本5g0.3%の購入が可能となっています。
-
シフランアイドロップ
1,800円~
在庫ありシフランアイドロップは細菌性の結膜炎やものもらいなど、細菌感染を原因とする諸症状に対して使用できる高い抗菌作用を有する点眼薬です。 ニューキノロン系抗菌薬に分類される有効成分が配合されており、ブドウ球菌やレンサ球菌など幅広い細菌に対して効果を発揮します。 細菌感染による症状は他人にも感染を広げる可能性があるため、早めにシフランアイドロップを使用して周りの人に感染させないことがとても重要です。
-
リレスタット(エピナスチン)点眼液
3,020円~
在庫なしリレスタット(エピナスチン)点眼液は、アラガン・ファーマスーティカルが製造販売している、抗アレルギーの点眼薬です。 有効成分としてエピナスチン塩酸塩が含有しており、主にアレルギー性結膜炎などの症状を改善する効果が期待できます。 第2世代の抗ヒスタミン薬に分けられており、アレルギー誘発物質の放出を抑制したり、炎症を抑えたりする作用があるとされているのが特徴です。 お薬通販部では、0.05%の購入が可能となっています。
-
アレルギーアイリリーフ
2,250円~
在庫なしアレルギーアイリリーフは、シラミサン社が開発したアレルギーによる眼症状であるかゆみや充血に対する点眼薬です。 通年性アレルギー・季節性の花粉症どちらも、鼻炎症状だけではなく眼症状も起こし、痒みから日常生活に支障をきたすこともあります。 あまりに症状が強いとこすったり叩いたりしがちですが、結膜炎を起こしているときにこれらをすると、網膜剥離や白内障を引き起こすこともあります。 アレルギーアイリリーフは、痒み・充血を伴う辛い眼症状に効果を発揮します。 お薬通販部では、1本10mlの購入が可能となっています。
-
ダイアモックス・ジェネリック(アセタゾラミド)
3,700円~
在庫ありアセタゾラミドは、インタスファーマ社が開発した炭酸脱水酵素抑制薬で、ダイアモックスのジェネリック医薬品です。 てんかんとは、てんかん発作を繰り返す脳の疾患で、脳内の神経細胞は微弱な電気的刺激で情報のやり取りが、突然の強い電気刺激により過剰に興奮した状態になります。 炭酸脱水酵素を阻害することで、脳のCO2濃度を局所的に増大させることにより、てんかんの発作のほか、緑内障・浮腫・メニエル病・月経前緊張症・高山病予防に使用されています。 お薬通販部では、アセタゾラミド250mgの購入が可能となっています。
眼病について詳しく説明!結膜炎から白内障・緑内障まで徹底解説!
目にはさまざまな病気がありますが、どんな薬がいいのかわからない方は多いのではないでしょうか。
結膜炎のような目の病気を防ぐためにはとにかく目やコンタクトレンズを清潔に保つことが大切です。
しかし、白内障や緑内障のような、加齢によって発症する病気もあります。進行度によって白内障のような手術が必要な病気でも効く薬があるため、おすすめの点眼薬を症状別でいくつか紹介します。
眼病に関するよくある質問はこちら
眼病についての疑問を持っている方から、以下の4つの質問が多く寄せられています。
- 眼病についての疑問
-
- カラコンやコンタクトの使用で眼病になる?
- ものもらいになったらどうしたらいい?
- 白内障と緑内障の違いは?
- 目の痒みを抑える方法は?
ここでは、眼病に関して多く寄せられている4つの質問にお答えします。
カラコンやコンタクトの使用で眼病になる?
カラコンやコンタクトの使用によって眼病になる可能性はあります。
使い方を間違えてしまうと充血や結膜炎の原因になりかねません。たとえば、1dayのコンタクトを一週間利用したり、コンタクトを外さずに寝てしまうと、充血などを引き起こす可能性が高いです。
決められた日数を守って、必要ないときは極力コンタクトを使うのは避けましょう。
ものもらいになったらどうしたらいい?
ものもらいになった場合は早急に適切な抗菌剤入りの目薬を使いましょう。
すぐ医師に相談できない場合は患部を冷やすことで多少痛みは和らげますが、治療には繋がりません。
ものもらいは細菌によって引き起こされるため、この細菌をなくさないことには治療はできません。小さくてすぐ吸収されるものもありますが、自己判断で治ったと判断するのは避けましょう。
白内障と緑内障の違いは?
白内障と緑内障は、どちらも目の疾患ですが、原因や症状と治療方法が異なります。白内障は、目の水晶体が濁ることで視力が低下する病気です。
白内障の原因としては加齢が主な要因であり、初期段階では視界がぼやける、色が黄色っぽく見えるなどの症状が現れます。白内障が進行すると、手術で濁った水晶体を取り除き、人工のレンズに置き換える治療が一般的です。
参考文献:公益財団法人 日本眼科学会「白内障」
一方緑内障は、視神経が損傷されることで視野が徐々に狭くなる病気です。
緑内障は通常、眼圧の上昇が原因とされていますが、眼圧が高くなくても発症する正常眼圧緑内障も存在します。
緑内障の症状は初期には気づきにくいですが、進行すると視野が欠け、最終的には失明に至ることもあります。
緑内障の治療は眼圧を下げるための点眼薬や手術が主な治療法です。
参考文献:公益社団法人 日本眼科医会「緑内障といわれた方へ―日常生活と心構え―」
白内障は視界のぼやけが主な症状で、手術で治療ができます。緑内障は視野の欠損が進行し、早期発見と眼圧管理が重要です。
目の痒みを抑える方法は?
目の痒みを抑える方法は主に4つあります。
- 目の痒みを抑える方法
-
- 冷たいタオルで冷やすことで、血管が縮小して痒みが軽減される
- アレルギー対応の目薬を使用することで軽減されるが、長期間使用する場合は医師に相談しましょう
- 目をこすってしまうと逆に炎症が悪化する可能性があるため、こすらずに冷やしたり、目薬を使ったりしましょう
- 空気洗浄機を使うことで、痒みの原因にもなる花粉や埃をなくしましょう
これらの対策を行っても症状が改善しない場合や、重症の場合は、眼科医に相談することが必要です。
眼病におすすめな点眼薬はこちら!
眼病におすすめの点眼薬を6つご紹介します。
| クララスティル | シーナック | フルメトロン点眼液 | カタリンK点眼用 | クラビット点眼薬 | ニフラン点眼液 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 1本あたり価格 | 5ml入 2,485円~ | 10ml入 2,160円~ | 5ml入 1,413円~ | 15ml入 1,283円~ | 5ml入 2,800円 | 5ml入 1,433円~ |
| 有効成分 | Nアセテルカルノシン、カルボキシメチルセルロース、p-ヒドロキシ安息香酸メチルなど | Nアルファ型アセテルカルノシン、カルボキシなど | フルオロメトロン | ピレノキシン | レボフロキサシン | プラノプロフェン |
| 効果 | 白内障改善 | 目の障害予防、老人性白内障改善 | 眼瞼炎改善、結膜炎などの改善 | 老人性白内障改善 | 結膜炎改善、ものもらい改善 | 結膜炎改善、角膜炎改善、眼瞼炎改善など |
| 製薬会社 | ブラスチェティニ・ソル | インタスファーマ | アルコン | 千寿製薬社 | 参天製薬 | 千寿製薬社 |
クララスティル
クララスティルは通常の治療法である手術とは異なり、点眼による手術のいらない治療方法として注目の治療方法です。
しかし、クララスティルは日本では医薬品として認可されていないため、主に個人輸入で購入されています。ただし、クララスティルの効果についてはまだ議論があり、全ての患者に有効であるとは限りません。
クララスティルを使用する際は自己判断ではなく、眼科医に相談することが推奨されます。薬機法に従い、使用や購入には十分な注意が必要です。

クララスティルは、白内障の進行を遅らせるために使用される点眼薬です。
主成分は「N-アセチルカルノシン(NAC)」という物質で、目の中で抗酸化作用を発揮します。
N-アセチルカルノシンの抗酸化作用によって白内障の原因となる酸化ストレスを軽減するとされています。
シーナック
シーナックは、クララスティルと同様に、白内障の治療のために使用される手術のいらない治療方法として注目の治療方法です。
しかし、シーナックは日本国内では医薬品として認可されていません。シーナックは主に個人輸入で入手されることが多く、使用にあたっては医師の監督下で行うことが推奨されます。
シーナックの効果には個人差があり、白内障の進行を完全に止めるものではないため、適切な医療機関での相談が重要です。薬機法に従い、使用や購入には十分な注意が必要です。

シーナック(Can-C)は、白内障の進行を抑えることを目的とした点眼薬です。
主成分は「N-アセチルカルノシン(NAC)」であり、この成分は抗酸化作用を持ちます。
N-アセチルカルノシンが目の中の酸化ストレスを減少させることで白内障の進行を遅らせるとされています。
フルメトロン点眼液
フルオロメトロンはアレルギー性結膜炎や手術後の炎症、角膜炎などに対応しています。
一方で、長期間使用すると眼圧の上昇や白内障のリスクが高まることがあるため、医師の指導の下で使用することが重要です。ステロイド系の点眼薬を使用している間は、眼圧を含む定期的な眼科検査が推奨されます。
また、長期間の使用は避け、医師の指示に従って適切な期間で使用することが求められます。フルメトロン点眼液は、強力な効果を持つ反面、副作用のリスクもあるため、医師の指示に従って使用することが非常に重要です。
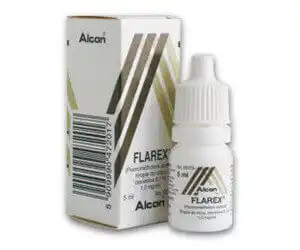
フルメトロン点眼液は、フルオロメトロンという成分を含むステロイド系の抗炎症点眼薬で、主に眼の炎症を抑える目的で処方されます。
フルオロメトロンは、結膜炎、角膜炎、虹彩炎などの炎症性眼疾患に対して使用され、目の炎症を強力に抑える効果を発揮します。
カタリンK点眼用
カタリンK点眼用は、比較的副作用が少ないとされていますが、まれに目の痒みや刺激を感じることがあります。
なお、カタリンK点眼用は白内障を根本的に治すものではなく、あくまで進行を遅らせるための薬です。
進行した白内障に対しては手術が唯一の治療法となるので、治療の効果や使用については、必ず眼科医の指導の下で行うことが重要です。

カタリンK点眼用は、白内障の進行を遅らせる目的で使用される点眼薬です。
主成分であるピレノキシンは、白内障の原因となる水晶体内のタンパク質の変性を抑える効果があります。
ピレノキシンは特に初期の白内障患者に対して進行を遅らせるために処方されることが多いです。
通常、1日数回の点眼が推奨され、長期間にわたって継続的に使用することで効果が期待されます。
参考文献:KEGG「医療用医薬品 : カタリン」
クラビット点眼薬
通常、1日3〜5回の点眼が推奨され、医師の指示に従って使用します。副作用は比較的少ないとされていますが、まれに目の痒みや違和感、まぶたの腫れが生じることがあります。
抗菌薬の使用には耐性菌のリスクが伴うため、指示された使用期間を守り、必要以上に長く使わないことが重要です。また、開封後は雑菌の混入を防ぐため、医師が指示した期間内に使用し、長期保存は避けるべきです。
クラビット点眼薬は、細菌性の眼疾患に対して有効ですが、自己判断での使用は避け、必ず医師の指導の下で適切に使用することが求められます。

クラビット点眼薬は、レボフロキサシンを有効成分とする抗菌点眼薬で、細菌による感染症を治療するために用いられます。
結膜炎、角膜炎、眼瞼炎など、目の表面に生じる細菌性の炎症や感染症に対して処方されます。
レボフロキサシンは幅広い種類の細菌に対して効果があり、細菌のDNA合成を阻害して感染を治療します。
ニフラン点眼液
通常、手術前後や炎症が発生した際に医師の指示に従い、1日数回点眼することが推奨されます。比較的安全な薬ですが、まれに目の刺激感や違和感、痒みを感じることがあります。
長期にわたる使用は避け、医師が指示した期間内で使用することが重要です。また、他の点眼薬や目の治療と併用する場合は、医師に相談することが推奨されます。
ニフラン点眼液は、手術後の炎症や外傷による目の炎症を効果的に抑えるために使用されますが、使用にあたっては必ず医師の指示に従うことが大切です。

ニフラン点眼液は、フルルビプロフェンという成分を含む非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の点眼薬です。
目の炎症や痛みを抑える目的で使用され、特に手術後の炎症や外傷による炎症の治療に用いられます。
フルルビプロフェンがプロスタグランジンという炎症を引き起こす物質の生成を抑えることで、炎症や痛みを軽減します。
コンタクトレンズはケアが大事!引き起こす可能性のある眼病とは
コンタクトレンズについてのケアや、引き起こされる眼病を紹介します。
トピックは以下の3つです。
- トピック
-
- コンタクトレンズの正しいケア方法
- 着用時間や睡眠前に外すことも大切
- コンタクトレンズが原因で起こる病気
コンタクトレンズの正しいケア方法
コンタクトレンズの正しいケア方法は、レンズの寿命を保ち、目の健康を守るために非常に重要です。
コンタクトレンズを装着する前に、必ず手を石鹸でしっかりと洗い、清潔なタオルで乾かしましょう。
手を清潔にすることで、レンズに細菌や汚れが付着するのを防げます。
正しい洗浄方法
手を清潔にするだけでなく、コンタクトレンズも清潔に保つことが大切です。
コンタクトレンズを外す際は、レンズケースに専用の消毒液を入れておくようにしましょう。
レンズを消毒液で十分にすすぎ、レンズケースに入れて保存します。レンズケース内の消毒液は毎日新しいものに取り替え、レンズケース自体も定期的に洗浄し、乾燥させて清潔を保つことが必要です。
着用時間や睡眠前に外すことも大切
コンタクトレンズは着用時間を守り、睡眠前に外しましょう。
コンタクトレンズを長時間装着していると、目の角膜が酸素不足に陥る可能性があります。コンタクトレンズは角膜に直接触れるため、酸素の供給が制限されます。
目が酸素不足になると、角膜の健康に悪影響を与え、感染症のリスクが高まります。また、目が乾燥しやすくなり、異物感や不快感が生じることもあります。
睡眠中にコンタクトレンズを着けたままですと、酸素供給が更に減少します。レンズが角膜に張り付いたり、傷をつけてしまうリスクが高いので、睡眠前は必ずレンズを外しましょう。
コンタクトレンズが原因で起こる病気
コンタクトレンズが原因で起こる病気を紹介します。
主に起こる病気は以下の3つです。
- コンタクトレンズが原因で起こる病気
-
- 角膜上皮障害
- 角膜潰瘍
- 結膜炎
角膜上皮障害
角膜上皮障害とは、目の角膜の表面を覆っている上皮層が傷つく状態のことを指します。
原因はコンタクトレンズの不適切な使用、目の外傷、乾燥、感染症などが挙げられます。
主な症状は目の痛み、異物感、涙目、光に対する過敏さなどがあり、適切な治療を行わないと、視力の低下や感染症のリスクが高まることがあります。
参考文献:日本医事新報社「角膜上皮疾患」(PDF)
角膜潰瘍
角膜潰瘍とは、角膜の表面にできる深い傷や感染による病変のことです。
原因は細菌、ウイルス、真菌の感染や、コンタクトレンズの不適切な使用、目の外傷などが含まれます。
主な症状は強い目の痛み、視力低下、目の充血、目やに、光に対する過敏さなどがあります。角膜潰瘍は放置すると視力を失う危険性があるため、早急な治療が必要です。
参考文献:MSDマニュアル(家庭版) 「角膜潰瘍」
結膜炎
結膜炎とは、目の表面を覆う結膜が炎症を起こす状態です。
原因はウイルスや細菌による感染、アレルギー、刺激物への反応などです。
主な症状は目の充血、痒み、涙目、目やにが増えるなどです。結膜炎は多くの場合軽度で治りますが、感染性の場合は治療が必要です。
結膜炎などを解決:クラビット点眼薬
クラビット点眼薬は、細菌性の目の感染症を治療するための抗菌点眼薬です。
クラビット点眼薬の主成分はレボフロキサシンで、結膜炎や角膜炎などに使用されます。クラビット点眼薬は細菌の増殖を抑えることで感染を治療します。

クラビット点眼薬は、参天製薬が開発した広範囲抗菌点眼薬です。
目に細菌が感染すると炎症をおこし、かゆみ・痛み・充血などがあらわれます。
クラビット点眼薬は、各種細菌や黄色ブドウ球菌などグラム陽性菌のほか、緑膿菌などのグラム陰性菌のDNA合成を阻害し、各種の細菌性外眼部感染症の炎症・充血などを改善します。
ものもらいになった場合の対処法!すぐ治したいときはどうすればいい?
ものもらいになったときの対処法をいくつか紹介します。
病院にすぐ行けない方は試してみてください。
- ものもらいになったときの対処法
-
- 目を清潔に保って細菌の増殖を軽減させましょう
- 1日に数回、数分間タオルで温めることで、腫れを和らげましょう
- 市販の抗菌目薬で症状の改善を助けましょう
- メイクやコンタクトレンズを避けることで、目を休めましょう
ものもらいは通常適切なケアで自然に治りますが、重症化を防ぐために医師の診断を受けることが重要です。
ものもらいの原因は二つ!麦粒腫と霰粒腫
ものもらいと一言で言っても、種類は一つではありません。主な原因は以下の2つです。
- ものもらいの原因
-
- 麦粒腫(ばくりゅうしゅ)
- 霰粒腫(さんりゅうしゅ)
麦粒腫(ばくりゅうしゅ)とは
麦粒腫とは、まつ毛の毛根やその周りにある皮脂腺が細菌感染によって炎症を起こすことで生じます。
麦粒腫はまぶたの腫れや痛みを伴うできもので、一般的には「ものもらい」とも呼ばれます。
参考文献:公益財団法人 日本眼科学会「麦粒腫」
霰粒腫(さんりゅうしゅ)とは
霰粒腫とは、まぶたにあるマイボーム腺が詰まり、炎症やしこりができる状態です。
霰粒腫痛みが少ないことが多く、自然に治ることもありますが、大きくなると外科的に取り除くことが必要になることもあります。
参考文献:公益財団法人 日本眼科学会「霰粒腫」
腫れや痒みを引き起こす!ものもらいの症状とは?
ものもらいの症状としては以下の2つです。
- ものもらいの症状
-
- まぶたの腫れ
- 目の痒みや痛み
まぶたの腫れ
まぶたの腫れは、目の周りに炎症や液体がたまることで起こる症状です。
軽度の場合は、冷やしたり休息を取ったりすることで改善することが多いですが、痛みや視力の変化を伴う場合は、眼科医の診察を受けることが重要です。
目の痒みや痛み
目の痒みや痛みがある場合、目をこすらず、適切な目薬を使用しましょう。
目を冷やすことで一時的に症状を和らげることもできますが、症状が続く場合や悪化する場合は、眼科医に相談することが重要です。
ものもらいをすぐ治したいときの対処法!
ものもらいをすぐに治したいときの対処法を紹介します。
おもな対処法は以下の3つです。
- ものもらいをすぐ治したいときの対処法
-
- 目を清潔な状態に保つ
- 温かいタオルで温湿布する
- 抗菌又はステロイド入りの目薬を使用する
目を清潔な状態に保つ
目を清潔に保つためには、目に触れる前に必ず手を洗い、コンタクトレンズは毎日適切に消毒し、保存することが大切です。
メイク用品は定期的に交換し、目をこすらず、目薬や洗眼でケアします。また、目を酷使しないよう、適度に休ませることも重要です。
温かいタオルで温湿布する
目を温かいタオルで温湿布することは、血行を促進し、目の疲れや緊張を和らげる効果があります。
また、ものもらいの症状である腫れや痛みの軽減にも役立ちます。
温かいタオルを目の上に数分間当てることで、目がリフレッシュされ、潤いが戻ることも期待できます。
抗菌又はステロイド入りの目薬を使用する
抗菌目薬は、細菌による感染症を治療するために使用され、感染の拡大を防ぎます。
一方、ステロイド入りの目薬は、炎症を抑える効果があり、アレルギーや炎症性の目の疾患に用いられます。
ただし、どちらも医師の指示に従って使用することが重要で、誤用すると副作用や症状の悪化を招く可能性があります。
ものもらい治療におすすめ:二フラン点眼液
二フラン点眼液は、フルルビプロフェンを有効成分とする非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の点眼薬です。 フルルビプロフェンは目の炎症や痛みを抑えるために使用されます。
二フラン点眼液は主に手術後の炎症や外傷による炎症の治療に用いられますが、使用は医師の指示に従うことが重要です。

ニフラン点眼液は、千寿製薬が製造・販売している点眼薬で、ステロイドが入っていないため副作用が少なく、安心してご使用頂けます。
有効成分は、プラノプロフェンです。この有効成分が、目の炎症や痛み、腫れ、発赤を抑えてくれます。
プラノプロフェンは、炎症や痛みに関与するプロスタグランジンの生成を促進する酵素の働きを抑制します。
白内障と緑内障はなにが違う?治療することはできるの?
白内障と緑内障の違いについて解説します。
また、それぞれ治療することが可能かどうかも合わせて解説します。
白内障と緑内障の違いについて解説
白内障は、水晶体が濁ることで視力が低下する病気で、視界がぼやけるのが主な症状です。
緑内障は、視神経が損傷されることで視野が狭くなる病気で、放置すると失明のリスクがあります。白内障は手術で治療可能ですが、緑内障は進行を抑えるために眼圧を下げる治療が必要です。
白内障
白内障は、目の水晶体が白く濁ることで視力が低下する病気です。
白内障は主に加齢が原因で、視界がぼやける、眩しさを感じるなどの症状が現れます。白内障が進行すると、手術で濁った水晶体を人工のレンズに置き換える治療が一般的です。
参考文献:公益財団法人 日本眼科学会「白内障」
緑内障
緑内障は、視神経が損傷されて視野が徐々に狭くなる病気です。
緑内障の主な原因は眼圧の上昇ですが、正常眼圧緑内障もあります。緑内障は自覚症状が少ないため、気づかないことが多く、進行すると失明のリスクがあります。
緑内障の治療は主に眼圧を下げる点眼薬や手術で行われます。
白内障と緑内障は治療することは可能?
白内障と緑内障は治療ができます。
- 白内障と緑内障は治療の可否
-
- 白内障は初期であれば点眼での治療が可能です。
- 緑内障は外科手術以外での治療は難しいです。
白内障は初期であれば点眼での治療が可能
初期の白内障で視力に大きな影響がない場合は、点眼薬や眼鏡の処方変更、生活習慣の改善で対処することができます。
しかし、進行した場合には手術が必要です。
緑内障は外科手術以外での治療は難しい
緑内障は薬で眼圧がコントロールできない場合や進行が見られる場合に、レーザー治療や外科手術が考慮されます。
外科手術は、あくまで他の治療法で効果が得られない場合に行われることが多いです。
初期の白内障治療に:クララスティル
クララスティルは、白内障の進行を遅らせるために使用される点眼薬で、N-アセチルカルノシンを主成分としています。 N-アセチルカルノシンは抗酸化作用を持ち、水晶体の濁りを抑えるとされています。
日本では医薬品として認可されておらず、主に個人輸入で入手されるので、使用には注意が必要です。

クララスティルはブラスチェティニ・ソル社が製造している白内障治療ができる点眼薬です。
従来の白内障治療用点眼薬とは症状の進行を遅らせることが目的で最終的には眼内レンズ挿入術という手術で治療するというのがスタンダードな方法でした。
しかしクララスティルは眼内レンズの酸化を抑制して濁りを防ぐという効果が確認されています。
目の痒みの原因は?痒くなった時の対処法はこちら
目の痛みの原因や、痒くなったときの対処法を解説します。自分の症状と照らし合わせて、適切な対処をしましょう。
目の痒みを引き起こす原因
目の痒みを引き起こす原因は、主に以下の3つです。
- 目の痒みを引き起こす原因
-
- 花粉
- ほこりやハウスダスト
- 動物などの毛
花粉
花粉が目に及ぼす影響は、アレルギー性結膜炎が代表的です。
アレルギー性結膜炎は、目に花粉が付着することで免疫反応が引き起こされ、目の痒み、充血、涙目、腫れなどの症状が現れます。
また、花粉によって目が乾燥しやすくなることもあります。症状を防ぐためには、花粉の多い時期には眼鏡をかける、外出後に目を洗浄する、抗アレルギーの目薬を使用することが有効です。
ほこりやハウスダスト
ほこりやハウスダストが目に及ぼす影響は、アレルギー性結膜炎が挙げられます。
ほこりなどの微粒子が目に入ると、免疫反応が引き起こされ、目の痒み、充血、涙目、異物感などの症状が現れることがあります。
また、ドライアイや炎症を引き起こすこともあります。症状を防ぐためには、定期的に部屋を掃除してハウスダストを減らす、目をこすらない、適切な目薬を使用することが効果的です。
動物などの毛
動物の毛やフケが目に及ぼす影響は、アレルギー性結膜炎が主な症状です。
動物の毛やフケに含まれるアレルゲンが目に入ると、免疫反応が起こり、目の痒み、充血、涙目、腫れなどの症状が現れます。
症状を予防するには、動物との接触後に手を洗う、目をこすらない、定期的に掃除を行い、部屋の清潔を保つことが大切です。必要に応じて抗アレルギーの目薬を使用することも有効です。
目が痒くなった時の対処法
目が痒くなった時の対処法を4つ紹介します。
- 目が痒くなった時の対処法
-
- 冷たいタオルで目を冷やす
- 目をこすらない
- 痒み止め成分を配合した目薬を使用する
- 目の痒みに効果的:フルメトロン点眼液
冷たいタオルで目を冷やす
目が痒くなった時に冷たいタオルで目を冷やすことで、痒みを軽減する効果があります。
目を冷やすことで、血管が収縮し、炎症やアレルギー反応が抑えられるため、痒みが和らぎます。
また、目を冷やすことで目の周りの腫れや不快感も軽減されることが多いです。痒みが強い場合や症状が続く場合は、適切な目薬を使用することも推奨されます。
目をこすらない
目が痒くなった時に目をこすらないことは、痒みや症状の悪化を防ぐために非常に効果的です。
目をこすると、さらに炎症がひどくなり、アレルギー反応が強まる可能性があります。
また、手に付着した細菌や汚れが目に入り、感染症のリスクが高まることもあります。目をこすらずに冷やしたり、適切な目薬を使用することで、痒みを安全に和らげることができます。
痒み止め成分を配合した目薬を使用する
目が痒くなった時に、痒み止め成分を配合した目薬を使用することで、痒みを迅速かつ効果的に緩和できます。
痛み止め成分は、抗アレルギー成分などが含まれており、アレルギー反応を抑え、痒みの原因となる物質の作用をブロックします。
また、目の炎症を鎮め、症状の悪化を防ぐことにも役立ちます。適切な目薬を使用することで、痒みが和らぎ、日常生活の快適さが保たれます。
目の痒みに効果的:フルメトロン点眼液
フルメトロン点眼液は、フルオロメトロンを主成分とするステロイド系の抗炎症点眼薬です。
フルメトロン点眼液は目の炎症を抑えるために使用され、結膜炎や角膜炎などの治療に効果的です。ただし、フルメトロン点眼液の長期使用は副作用のリスクがあるため、医師の指示に従って使用することが重要です。
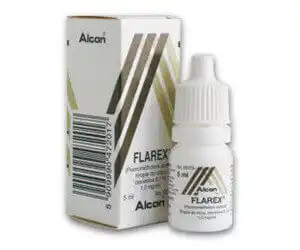
フルメトロン点眼液は、アルコンが開発した抗炎症ステロイド点眼薬です。
アレルギー性の結膜炎は、花粉症やハウスダスト以外にアトピーや春季カタルに代表され目頭のかゆみがあらわれます。
抗アレルギー剤・ステロイド・免疫抑制剤・内服薬の使用で炎症による腫れや赤みを改善します。
眼病治療薬の口コミはこちら
目や手を清潔に保ち、コンタクトレンズやカラコンを適切に使うことが眼病のリスクを下げることがわかりました。
こちらで紹介した対処法が実践できれば、ある程度は症状の軽減が見込めますが、医師の診察および処方を受けるのが原則です。最後に、ご紹介した薬を実際に使ってみた方の口コミも参考にしてください。
クララスティルの口コミ
- いいクチコミ
-
大田さん 55歳
白内障のため治療していましたが、眼科が合わずに通院を辞めてしまいこちらの商品を使い始めました。症状が良くなっているので合っていると思います。
- 悪いクチコミ
-
イチ 51歳
若年性白内障と診断され、症状に悩んでいましたがこちらの目薬を使うようになり眩しさが少し軽減されてきたと思います。目の濁りは消えませんでした。
シーナックの口コミ
- いいクチコミ
-
misa 58歳
白内障の治療で利用しています。病院に行くのが大変なので、通販で購入できて助かっています。病院で処方される薬となんらかわりません。また利用させてもらいます。
- 悪いクチコミ
-
だい 53歳
こちら1本使いましたがあまり効果を感じませんでした。もっと継続すれば効果が出るかもしれません。
フルメトロン点眼液の口コミ
- いいクチコミ
-
さくら 34歳
アレルギーでときどき目に症状がでてしまうのですが、これがあればすぐに症状を緩和できるので、とても助かっています!市販薬はここまで効かないので、本当にありがたいです。
- 悪いクチコミ
-
キャス 28歳
点眼液なので飲む薬よりは効果があるかなと期待していたのですが、あまり目のかゆみは収まりませんでした。今度は飲む方の薬を試してみます。
カタリンK点眼用の口コミ
- いいクチコミ
-
nontan 28歳
1本目を使い切ったところですが効果あります!目の疲れやかすみがキレイにとれるのでありがたいです。仕事場にも常に置いてあります。
- 悪いクチコミ
-
山さん 59歳
白内障の治療のために使い始めましたが、私にはあまり相性が良くなかったのか、特に効果を感じることができませんでした。 今後も飲み続けるかは医者と相談しようと思います。
クラビット点眼薬の口コミ
- いいクチコミ
-
ポッケ 35歳
ものもらいになりやすく、常にストックしてあります。症状が速めに落ち着きすぐに治るようになりました。かゆみや違和感も目薬をすると良くなります。
- 悪いクチコミ
-
マッシュ 41歳
目の充血が治ったような、特に変化がないような。少し価格も高いように思いましたが、とりあえずもう少し使ってみようと思う。
ニフラン点眼液の口コミ
- いいクチコミ
-
よっちゃん 29歳
目が腫れるときに使っています。何日か使うと、症状がよくなります。副作用などもないので、これからも利用する予定です。薬局で売っているのは効果がないって人も試してほしいです。
- 悪いクチコミ
-
くろ 47歳
急に角膜炎にかかってしまい、こちらを処方されました。なんかかゆみが出たり目やにが多くなったような気がします。