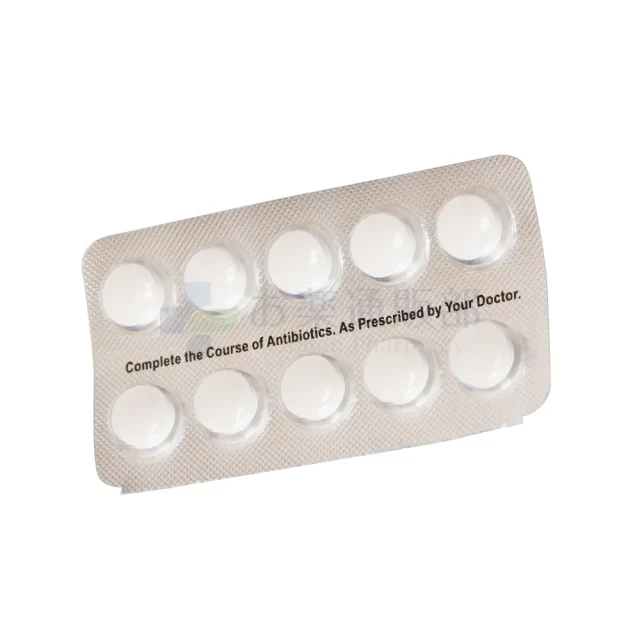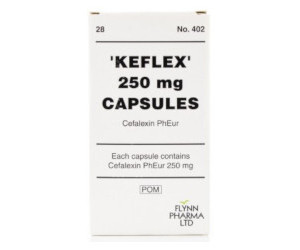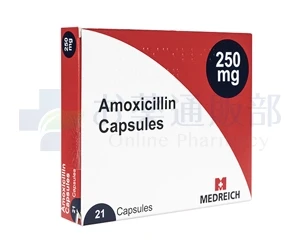梅毒
梅毒の治療薬通販ページです。梅毒などに有効な細菌感染症の治療薬を最安値でご紹介しています。
梅毒人気ランキング
梅毒の商品一覧
現在の検索条件
-
ノバモックス(シロップ)
1,940円~
在庫ありノバモックスはペニシリン系の抗生物質でサワシリンやパセトシンのジェネリック医薬品です。 ノバモックスはシロップタイプのため、小児も服用しやすく体内での吸収がされやすいため、錠剤タイプの医薬品を敬遠している方でも服用が容易です。 お薬通販部では、125mg/250mgの購入が可能となっています。
-
ディヴァイン
2,840円~
在庫なしディヴァインは、シプラが開発したテトラサイクリン系抗菌薬で、クラミジア治療薬であるミノマイシンのジェネリック医薬品です。 ディヴァインは細菌の蛋白質合成を阻害することから、クラミジアを始めとして、多くの種類の細菌および感染症の治療に効果を示します。 テトラサイクリン系抗菌薬において、組織移行性が良好で生体内半減期も長く、作用持続時間が長いのが特徴です。 成人は100~200mgの服用が推奨され、 小児は、体重1kgあたり2~4mgを1日量とした服用が推奨されます。 【ニキビの場合】 ・1~3週間継続服用 【クラミジア感染症の場合】 ・1~2週間継続服用 >>服用期間の目安はこちら お薬通販部では、50mg/100mgの購入が可能となっています。
-
サワシリン・ジェネリック(ノバモックス)
6,180円~
在庫ありサワシリン・ジェネリック(ノバモックス)は、ペニシリン系の抗生物質「アモキシシリン」を主成分とする医薬品、サワシリンのジェネリック医薬品です。 ノバモックスはサワシリンと同じく細菌感染を原因とする淋病や梅毒といった性感染症のほか、咽頭炎、気管支炎、前立腺炎、子宮内感染症などに効果があります。
-
ミノマイシン・ジェネリック(ミノシン)
3,100円~
在庫ありミノシンは、抗生物質のひとつミノサイクリンを配合したジェネリック医薬品です。 肺炎、胃腸炎、咽頭炎のほか、皮膚感染症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染対策、尿道炎、淋菌感染症、梅毒、細菌性腟炎、子宮内感染といった泌尿器系、性病関連の殺菌にも効果を発揮します。
-
ビクシリン・ジェネリック(アンピシリン)
4,580円~
在庫ありカディラ・ファーマシューティカルズの開発したビクシリン・ジェネリックは、日本のMeiji Seika ファルマ株式会社が開発したビクシリンのジェネリック医薬品です。 梅毒や淋病などの性病は、性器の嫌な匂い、かゆみや痛み、発疹など原因となり、パートナーへ感染するリスクもあります。 ビクシリン・ジェネリックは梅毒や淋病などの感染症や炎症に効果を発揮し、処方箋も必要ありません。 【推奨用量】 通常、成人は1回250mg~500mgを1日4~6回経口投与することが推奨されます。 年齢や症状に応じて適宜増減量を行う必要がありますので、かかりつけ医師へご相談ください。 お薬通販部では、250mg/500mgの購入が可能となっています。
-
アイケア・梅毒検査キット
2,300円~
在庫なし梅毒は梅毒トレポネーマという病原菌が原因となって起こる性感染症(STD)の一種で、痛みや痒みなどの自覚症状が乏しく、仮に症状があっても無治療のままで症状が消失し、一度治癒したかのような経過をたどる特徴があります。 適切な治療を受けないまま血液を介して病原体が全身にまわってしまうと、数か月後に全身の発疹となって現れ、場合によっては多臓器への影響を起こすこともあります。 また、妊娠した女性が梅毒に感染すると、死産・早産・新生児死亡・奇形のリスクが高くなります。
-
セファレキシンカプセル
2,430円~
在庫なしセファレキシンカプセルは、セフェム系の抗生物質であるセファレキシンを含んだカプセルタイプの医薬品で、イギリスの製薬会社フリンファーマが開発・販売を行っています。 細菌感染症治療薬ケフレックスカプセルのジェネリック医薬品にあたり、淋病や梅毒といった性感染症のほか、咽頭炎、皮膚感染症、歯周病などの治療に用いられる汎用性の高い治療薬です。
梅毒は治療薬で治る?完治しない?市販や通販の薬で症状を治す方法
日本国内で近年感染者が急増している性病として。梅毒が注目されているのはご存じですか?
梅毒は治療せずに放置していると死に至る恐れもあるため、早めに対処しなければいけません。今回は梅毒に効くおススメの治療薬や、市販及び通販で梅毒の治療薬は購入できるのかについて解説していきます。
梅毒の治療についてよくある質問
梅毒の名前は知っていても主な症状や治療方法など、詳細について知らない方は多いのではないでしょうか?まずは梅毒に関する、よくある質問と回答をまとめましたのでご覧ください。
梅毒の感染原因はなんですか?
梅毒の主な感染原因は性行為です。梅毒は梅毒トレポネーマと呼ばれる細菌に感染すると発症しますが、この細菌は口や性器周辺に多く潜んでいます。
細菌が存在する場所と粘膜接触又は皮膚接触すると感染するため、オーラルセックスやアナルセックスなど性行為に類する行為でも感染する可能性があります。
梅毒は治療薬で治りますか?
昔は不治の病として多くの人を苦しめてきた梅毒ですが。現在は抗生物質の使用で完治が目指せます。
ただし、症状が進行すると治療が難しくなり、後遺症が残ったり完治できなくなったりする恐れがあります。梅毒は早期発見が何より重要です。
梅毒の薬はドラッグストアなどの市販で購入できますか?
梅毒の治療薬は医師の処方箋が必要な処方せん医薬品に分類されるため、ドラッグストアなど市販では販売されていません。
梅毒の市販薬の入手方法はありますか?
前述の通り梅毒の市販薬は販売されていないので、市販での入手方法はありません。もし梅毒の治療薬が市販されていた場合、偽物の可能性が非常に高いので購入しないようにしましょう。
Amazonや楽天で梅毒の薬は購入できますか?
市販と同様にAmazonや楽天など、大手の通販サイトでも梅毒の治療薬は販売されていません。通販で梅毒の治療薬が購入できるサイトは、お薬通販部のような薬を専門に取り扱っている個人輸入サイトのみです。
梅毒の薬を個人輸入代行などの通販での購入は安全ですか?
個人輸入代行は市販では販売されていない梅毒の治療薬を、通販で購入できる数少ないサービスです。個人輸入代行はとても便利なサービスですが、運営会社がしっかりしているところでなければ購入時にトラブルに遭うケースが考えられます。
お薬通販部はメーカー正規品のみを取り扱っている、安全性に優れた特徴を持つ通販サイトの一つです。市販されていない医薬品も販売しており、その他のユーザーサポートも整っています。初めて個人輸入代行を利用する方でも、安心してご使用いただけます。 品揃えも豊富なので、梅毒の治療薬だけでなくその他の薬を通販購入したい方も必見の通販サイトです。
梅毒の治療に効く抗生物質や治療薬は?感染原因や治し方について
梅毒は細菌感染が原因となるため、細菌の増殖を抑える抗生物質の使用がとても有効です。特に感染初期に使用すると、高い治療効果が期待できます。
抗生物質を配合した薬はいくつか市販されていますが、梅毒に効果がある抗生物質は市販されていません。梅毒に効果がない市販の抗生物質を、梅毒の治療目的で使用するのは止めましょう。
続いて、梅毒に感染すると起きる主な症状や、詳しい治療方法についてご紹介します。
参考文献:梅毒に関するQ&A|厚生労働省
| ビクシリン・ ジェネリック (アンピシリン) |
ディヴァイン | ジスロマック | |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
|
| 種類 | ペニシリン系 | テトラサイクリン系 | マクロライド系 |
| 有効成分 | アンピシリン | ミノサイクリン | アジスロマイシン |
| 特徴 | カディラ・ファーマシューティカルズが開発したビクシリン・ジェネリックで、梅毒や淋病などの感染症や炎症に効果を発揮します。 | ディヴァインはシプラが開発したテトラサイクリン系抗菌薬で、細菌の蛋白質合成を阻害することから、クラミジアを始めとする多くの細菌および感染症の治療に効果を示します。 | ジスロマックは大手製薬会社ファイザーが開発したマクロライド系抗生物質で、性器クラミジア感染の治療にも有効で、効果が期待できます。 |
| 価格 | 1錠 48円~ | 1錠 160円~ | 1錠 676円~ |
梅毒の症状は?第1期から第4期に分けられる
梅毒は治療せずに放置していると、症状が進行していく病気です。進行具合によって、4つのステージに分けられます。
| ステージ(感染からの日数) | 主な症状 |
|---|---|
| 第1期(初期感染~3週間) | 性器・肛門・口にできものやしこり、ただれ |
| 第2期(1~3か月) |
|
| 第3期(3~10年) | 顔、身体、手足、骨、筋肉にゴム腫 |
| 第4期(10年以上) |
|
第4期は末期症状で、ここまで進行した梅毒を治療するのは、現代の医学でも困難だと言われています。
男性の梅毒の症状は?
梅毒は男性と女性で、症状の現れる場所が異なります。男性が梅毒に感染すると、以下に紹介する症状がそれぞれの場所で発生します。
初期硬結(男性の場合)
初期硬結は梅毒の感染初期に現れる症状の一つで、感染部位に硬いしこりができます。男性の場合は、主に亀頭や陰茎、冠状溝(亀頭と陰茎の間の部位)や口に症状が現れます。
痛みの伴わないしこりができるため、症状に気付かず見逃しやすいです。
硬性下疳
硬性下疳は初期硬結ができた場所の中心に、潰瘍ができる症状です。皮膚がただれたような状態になるため、一目で症状が確認できます。
バラ疹
治療が遅れて梅毒の原因菌が全身に広がってしまうと、全身にブツブツの発疹ができるようになります。これをバラ疹と呼びます。赤い斑点のような模様ができるものの、痛みや痒みといった症状は特に現れません。
女性の梅毒の症状は?
女性が梅毒を発症した場合も、男性と同じような症状が現れます。一つ一つの症状を、詳しく見ていきましょう。
初期硬結(女性の場合)
女性が初期硬結を発症すると、主に膣内や大陰唇及び小陰唇の周辺にしこりができます。自分では見えにくい場所にできやすく、男性以上に気付きにくいのが難点です。
扁平コンジローマ
性器や肛門の周辺にピンク又は灰色をした、平べったいイボができる病気です。発症すると軽い痛みや痒みなどの不快感を伴います。
梅毒性アンギーナ
梅毒性アンギーナは喉や扁桃腺に、梅毒の細菌が感染すると発症する病気です。喉や扁桃腺の粘膜が、赤く腫れたりふやけたりなどの症状が現れます。
梅毒などの性感染症は自然治癒しない!放置で死亡する確率は?
梅毒を含む性感染症の多くは、適切な治療を施さなければ完治することはありません。特に梅毒は死に至る病として江戸時代にとても恐れられた病気で、当時の致死率は20~40%程度と言われています。
現代の梅毒の致死率は発表されていません。しかし、第4期まで治療せずに放置すると日常生活に支障をきたす障害や、命に関わる状態になる恐れがあります。
早期発見で治療が重要!梅毒の疑いがあるなら検査を
梅毒の治療は「早期発見&早期治療」の2つが重要です。もし梅毒の感染が疑われる方と性行為や性行為に類する行為をした場合は、早めに検査をして感染の有無を確認しましょう。
梅毒の検査の方法は?市販のキットや病院で可能!
- 梅毒の検査方法
-
- 病院を受診
- 市販で梅毒専用の検査キットを購入 など
病院での検査は病院へ行く手間はありますが、高精度の検査が受けられるのが魅力的です。市販の検査キットは自宅で検査できるので、内緒で梅毒の検査をしたい方におススメです。
梅毒の検査結果はいつ分かる?
梅毒の検査をしてから、どれくらいで検査結果が分かるのか気になりますよね?
以下に病院と市販の検査キットを使用した場合、検査結果が分かるまでどれくらいかかるのかまとめましたのでご覧ください。
| 検査方法 | 検査結果が分かるまでの期間 |
|---|---|
| 病院での検査 | 即日若しくは1~3日程度 |
| 市販の検査キット(自宅で完結するタイプ) | 15~30分程度 |
| 市販の検査キット(検査体を郵送するタイプ) | 4日~7日程度 |
市販の検査キットは検査方法が間違っていると、陽性であっても陰性の結果が出る可能性があります。市販の検査キットで陰性が出ても梅毒が疑われる症状が現れている場合は、念のために病院を受診した方がいいでしょう。
梅毒の感染経路に心当たりがない!性感染症の原因は?
梅毒の感染経路で最も多いのは性行為です。しかし、性行為をしていなくても梅毒に感染する可能性はあります。以下のようなケースが、感染経路の一例として挙げられます。
- 感染経路ケース
-
- オーラルセックス
- キス
- 素手で性器に触れる
- 皮膚と病変部が触れるなど
また、梅毒は潜伏期間が長い病気で、感染してから数週間経って症状が現れてくることがあります。直近で感染経路に心当たりがない方は、数週間遡って感染原因を探ってください。
梅毒は薬で治る!病原体に効く治療方法は抗生物質
梅毒は原因となる梅毒トレポネーマを死滅させる抗生物質を使用することによって治療できます。しかし、抗生物質であれば何でもいいというわけではなく、梅毒トレポネーマに対して殺菌効果を持つ抗生物質を選んで使用する必要があります。
梅毒の薬の種類は?抗生物質と注射での治療を解説
梅毒の薬はいくつかありますが、それぞれ配合されている有効成分や剤形が異なります。種類も豊富なので、梅毒の治療薬を市販や通販で購入しようとした場合、どれがどんな効果を持っているのか分かりにくいです。
続いて、梅毒に有効な治療薬の種類や治療薬の特徴を解説していきます。
梅毒の初期治療の発熱は副作用ではない!
梅毒の治療薬を使用すると、治療初期の段階で発熱や全身の倦怠感などの症状が現れます。この症状は「ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応」と呼ばれています。ヤーリッシュ・ヘルクスハイマー反応の特徴は以下の通りです。
- 特徴
-
- 治療薬によって梅毒トレポネーマが大量に死滅した際に起きる症状
- 症状は一過性で、すぐに治まる
- 全ての人に起こる反応ではない
梅毒のペニシリン系抗生物質の治療薬と種類は?
梅毒の治療薬は、抗生物質の系統によって分けることができます。まずは抗生物質の中でもとくに有名な、ペニシリン系抗生物質に分類される治療薬を2つご紹介します。
| 商品名 | 製造会社 | 販売価格 |
|---|---|---|
| アモキシシリン | ブリストル・ラボラトリーズ | 21錠入り1,430円 |
| ビクシリン・ジェネリック | カディラ・ファーマシューティカルズ | 100錠入り4,300円 |
どちらも市販での取り扱いはありませんので、欲しい方はお薬通販部をチェックしてみましょう。
アモキシシリン

アモキシシリンはサワシリンやパセトシンのジェネリックに該当する抗生物質で、優れた殺菌作用を有する有効成分が配合されています。梅毒だけでなく淋病に対しても、高い治療効果を発揮します。
ビクシリン・ジェネリック(アンピシリン)

ビクシリン・ジェネリックは日本の製薬会社「明治製菓ファルマ」が開発したビクシリンのジェネリック医薬品です。100錠入りの大容量に加えて1錠当たりの価格がとても安いので、梅毒の治療に掛かる費用を抑えることができます。
梅毒のテトラサイクリン系抗生物質の治療薬と種類は?
テトラサイクリン系の抗生物質も、梅毒に対して優れた治療効果を持っています。主な治療薬は以下の通りです。
| 商品名 | 製造会社 | 販売価格 |
|---|---|---|
| ディヴァイン | シプラ | 10錠入り2,840円 |
| アカミン | アルファファーム | 60錠入り3,880円 |
| ミノマイシン・ジェネリック | テオファーマ | 1箱(12錠入り)2,950円 |
ディヴァイン

ディヴァンは梅毒・淋病・クラミジアなど、幅広い性感染症に用いられている抗生物質の一つです。体内で有効成分がゆっくり溶けるため、1回の服用で長時間効果が持続します。
ニキビの原因菌であるアクネ菌の増殖を抑える効果もあり、ニキビ治療の内服薬としてもご使用いただけます。
アカミン

アカミンは有効成分にミノサイクリンを配合した、高い抗菌作用を有する治療薬です。ミノマイシンのジェネリック医薬品で、有効成分の全身への移行性の高さに優れています。
ミノマイシン・ジェネリック(ミノシン)

ミノマイシン・ジェネリックはイタリアに本拠地を置く、テオファーマ社が製造販売しているミノサイクリン配合の抗菌薬です。
細菌のタンパク質合成を阻害する作用によって、細菌の増殖を抑制して諸症状を緩和します。ジェネリックなので先発薬より安く購入できる点にも要注目です。
梅毒のマクロライド系抗生物質の治療薬とは?
マクロライド系抗生物質は梅毒に対してあまり適応が無いと言われています。そのため、梅毒の治療薬として使われることは殆どありません。マクロライド系抗生物質を梅毒の治療目的で使用しないでください。
ベンジルペニシリンベンザチン筋肉注射薬について
「ベンジルペニシリンベンザチン筋肉注射薬」は内服薬ではなく、注射によって梅毒の治療ができる医薬品です。
アメリカCDC(アメリカ疾病予防管理センター)のガイドラインにおいて、梅毒の治療薬として使用することが推奨されています。しかし、日本では過去に使用した方がショック死した事例があり、現在では国内で梅毒治療に使用されることはありません。
梅毒の治療薬を通販や市販で購入する方法は?正規品を入手する方法
梅毒を含む性感染症は、感染した事実を他人に知られたくない方が多い病気の一つです。できるなら病院へ行かず、市販や通販で購入できる薬で治したいと思っている方も多くいらっしゃいます。
続いて、市販及び通販で梅毒の治療薬を購入する方法及び、安全な治療薬の入手方法について解説していきます。
個人輸入サイトは処方箋なしで梅毒の治療薬を購入できる
梅毒の治療薬を国内で入手しようとした場合、病院を受診して医師から処方箋を出してもらわなければいけません。
個人輸入サイトは市販で販売されていない薬を取り扱っている通販サイトで、処方箋が無くても梅毒の治療薬が購入できます。個人輸入サイトは一般的な通販サイトと同じような感覚で利用できます。これまで通販サイトを利用したことがある方なら、戸惑うことなく購入可能です。
ちなみにドラッグストアや薬局など、市販では梅毒の治療薬は購入できないので注意してください。
病院での診察には治療薬代の他に別途費用がかかる
梅毒で病院を受診すると治療薬代に加えて受診代や処方箋代、病院へ行くまでの交通費が追加で掛かります。さらに完治するまで複数回受診しなければいけませんので、トータルの費用は高額になりやすいです。
価格は圧倒的に通販がお得!
個人輸入サイトのような通販サイトで梅毒の治療薬を購入する場合、必要となる費用は治療薬代と送料のみです。さらに、お薬通販部では10,000円以上以上購入することによって、送料無料になるといったサービスもございます。そのため、病院を受診して治療薬を貰うより遥かに安く購入できます。
梅毒は感染後に免疫を獲得できる病気ではないため、梅毒感染者との接触で何度でも感染する恐れがあります。通販で治療薬を購入すれば、感染の度に病院へ行く手間が省けると同時に費用も節約できます。
梅毒の治療薬を通販で購入した場合即日届くのか?
梅毒の治療は早い段階で始めるのが有効なので、治療薬は早めに欲しいですよね?通販で梅毒の治療薬を購入した場合、お届けまで時間が掛かってしまいます。
一方、病院で梅毒の治療薬を処方してもらう場合、その日のうちに治療薬は入手できます。すぐに梅毒の治療薬が欲しい方は、病院を受診するのがおススメです。
通販は発送から届くまでに時間がかかる
個人輸入サイトで治療薬を通販購入すると、自宅に届くまでどれくらい掛かるのでしょうか?
お薬通販部を例に挙げると、注文完了からお届けまでおよそ10~28日掛かります。国内の通販サイトのように、即日や数日以内に届くといったことはありません。通販で治療薬を購入する際は、時間に余裕をもって注文しましょう。
梅毒の治療薬の偽物に注意しよう!
梅毒は世界中に多くの感染者がいるため、治療薬の需要も非常に多いです。人気の商品は本物に紛れて偽物が市販で数多く出回りますが、医薬品も例外ではありません。
市販及び通販では、梅毒の治療薬を名乗る偽物が存在します。梅毒の治療薬は国内において市販での販売が認められていないため、市販で梅毒の治療薬があった場合はほぼ偽物と考えられます。
安全に正規品を入手したい方は病院で処方してもらうか、お薬通販部のような正規品のみを取り扱っている個人輸入サイトを利用して通販購入してください。
梅毒の薬を飲んでも治らない原因は?病原体はどうなってるの?
梅毒は梅毒トレポネーマに適応した抗生物質を使用することで、高確率で治すことが可能な病気です。しかし、下記のいずれかに該当する場合は、薬を飲んでも治らないケースがあります。
- 治らないケース
-
- 治療中に感染者と性行為をした場合
- 服用方法を守っていない場合
- HIVに感染している場合
もし、通販で購入した梅毒の治療薬を使用しても症状が改善しないときは、医師の診察を受けるようにしてください。
梅毒はどれくらいで治る?
梅毒は症状の進行具合によって、下記のように完治までの期間が変わります。
| 症状の進行具合 | 完治までの期間 |
|---|---|
| 第1期 | 2~4週間 |
| 第2期 | 4~8週間 |
| 第3期以降 | 8~12週間 |
このように症状の進行が進んでいない状態から治療を開始すれば、早めの完治が期待できます。梅毒に感染しやすい方は、事前に通販で梅毒の治療薬を購入しておくのがおススメです。
完治しない状態で性行為は大丈夫?
梅毒が完治していない状態で性行為をすると、パートナーも梅毒に感染してしまいます。性行為は梅毒が完治するまで控えるようにしてください。
治療薬を飲み忘れた場合の性感染症治療法
梅毒の治療薬を飲み忘れてしまうと、治療効果が減退する恐れがあります。細菌が薬に対して耐性を得る可能性もあるため、飲み忘れないようにしましょう。
梅毒の治療薬の副作用を種類別に紹介
梅毒の治療薬は病院で処方されたもの及び通販で購入したもの、どちらであっても使用時に副作用を起こす可能性があります。
事前にどのような副作用が起きるか把握しておくと、副作用が起きても素早く対処できます。治療薬の種類別にどのような副作用が起きるのか解説していきます。
アモキシシリンの副作用について
ペニシリン系抗生物質に分類されるアモキシシリンは、幅広い細菌感染症の治療薬として用いられています。優れた抗菌作用を持つアモキシシリンですが、服用方法を守っていても人によって副作用を起こすことが分かっています。
主な副作用
- アモキシシリンの主な副作用
-
- 発疹
- 好酸球過多
- 嘔吐、下痢
- 悪心
- 食欲不振
- 腹痛 など
注意が必要な副作用
- アモキシシリンの重篤な副作用
-
- アナフィラキシーショック
- 中毒性表皮壊死融解症
- 皮膚粘膜眼症候群
- 肝障害
- 腎障害
- 無菌性髄膜炎
- 大腸炎
- 間質性肺炎 など
重篤な副作用を起こした場合は、すぐに使用を中止して医師の診察を受けてください。
ビクシリンの副作用について
ビクシリンもアモキシシリンと同様、ペニシリン系抗生物質に分類される治療薬です。梅毒や淋病の治療薬として昔から使われてきましたが、以下に紹介する副作用を起こすことが報告されています。
主な副作用
- ビクシリンの主な副作用
-
- 発熱
- 発疹、蕁麻疹
- 下痢
- 悪心
- 食欲不振 など
上記の副作用が起きた際は、経過観察を十分に行うようにしましょう。
注意が必要な副作用
- ビクシリンの重篤な副作用
-
- アナフィラキシーショック
- 中毒性表皮壊死融解症
- 皮膚粘膜眼症候群
- 無顆粒球症、溶血性貧血
- 急性腎障害
- 偽膜性大腸炎
- 肝機能障害 など
いずれも命の危険を伴う症状ばかりなので、万が一これらの症状が確認できた場合は必ず医師の診察を受けてください。
ミノマイシンの副作用について
ミノマイシンはテトラサイクリン系抗生物質に分類され、抗菌力は他のテトラサイクリン系抗生物質より高いと言われています。また、長期間服用しても耐性菌ができにくい特徴を有しています。しかし、他の治療薬と同じように副作用の発症リスクはあるため、使用時は注意が必要です。
主な副作用
- ミノマイシンの主な副作用
-
- めまい
- 悪心
- 嘔吐
- 食欲不振
- 腹痛 など
副作用の発症頻度はそれほど高くありませんが、使用時はこれらの症状に注意してください。
注意が必要な副作用
- ビクシリンの重篤な副作用
-
- アナフィラキシーショック
- ループス様症候群
- 結節性多発動脈炎
- 顕微鏡的多発血管炎
- 自己免疫性肝炎
- 中毒性表皮壊死融解症
- 皮膚粘膜眼症候群
- 薬剤性過敏症症候群
- 血液障害
- 肝機能障害
- 急性腎障害
- 間質性肺炎
- 呼吸困難
- 膵炎
- 出血性腸炎、出血性大腸炎
- 精神神経障害 など
いずれも発症頻度は不明ですが、もし発症すると重篤な事態に陥るため注意が必要です。
梅毒の治療薬の併用禁忌
医薬品は注意が必要な併用注意と、併用は絶対してはいけない併用禁忌の2つがあります。
梅毒の治療薬には併用禁忌とされる医薬品はありません。しかし、併用注意とされる医薬品は存在します。併用に注意すべき医薬品は以下の通りです。
| 商品名 | 併用注意に該当する薬剤 |
|---|---|
| アモキシシリン |
|
| ビクシリン |
|
| ミノマイシン |
|
通販で梅毒の治療薬を購入して使おうと思っている方は、上記の薬と併用しないように気を付けるか、医師と併用について事前に相談してください。
梅毒の治療薬を服用してはいけない人は?
梅毒の治療薬は誰もが使用できるわけではなく。下記に該当する人は服用することができません。
- 該当する人
-
- それぞれの薬剤でアレルギー症状を起こしたことのある方
- 伝染性単核症をお持ちの方 など
梅毒の治療薬の口コミまとめ
梅毒の治療薬は市販では入手できないため、治療薬が欲しい方は病院を受診するか個人輸入サイトで通販購入するかの2択です。
梅毒が流行している今、気軽に購入できる個人輸入サイトが注目されています。個人輸入サイトでは梅毒の治療薬だけでなく、梅毒の検査キットも販売されています。頻繁に梅毒に感染する方は検査キットをストックとして保管しておくことをおススメします。
梅毒の治療は初期段階で始めるのが何より重要なので、今回紹介した梅毒の治療薬を使用して早期治療を心がけましょう。
ディヴァイン
- いいクチコミ
-
桜井れいか (54歳)
性感染症の、薬を、こんな、時代で、病院にいけないときに、お守りで、もっておきたいです。
- 悪いクチコミ
-
みっちゃん (40歳)
ディヴァイン(Divaine-100)を通販で手に入れ、クラミジア治療に使用しました。効果は高かったですが、副作用が少し気になりました。
アジー
- いいクチコミ
-
AOI (23歳)
クラミジア治療で購入しました。かなり高かったので効かなかった時のことを考えると怖かったんですが、しっかり効いてくれたので安心しています。副作用がいろいろあるようですが、私はどれも起きませんでした。
- 悪いクチコミ
-
サワラ
セックス後違和感があったので、azee1000を6錠購入し、1錠飲みましたが変化は無く、3日間続けて飲んだら、下痢が酷くまたあまり変化がありませんでした。
ミノマイシン・ジェネリック(ミノシン)
- いいクチコミ
-
ロック (39歳)
以前クラミジアに罹って病院へ行ったことがあるので、また行くのが恥ずかしく、こちらで薬を購入させてもらいました。初めてネット通販で薬を買ったので不安でしたが、しっかりクラミジアの症状は改善できました。
- 悪いクチコミ
-
理子 (29歳)
クラミジアになったのでこれを購入して2週間くらい飲み続けたけど、殆ど症状は改善できなかったです。なので結局病院へ行って薬をもらい、その薬で治療することができました。薬と私の身体が合ってなかったのかな?
ノバモックス(シロップ)
- いいクチコミ
-
MOON (36歳)
いろいろな性感染症に対して効果があるので、これさえ持っていれば怖いものなし!ドリンク気分で気軽に服用できるのも最高!こういうお薬って錠剤が多いイメージだったけど、こういうのもあるんだと知れて良かったです♪
- 悪いクチコミ
-
よーちゃん (41歳)
錠剤が苦手でこれなら飲めるはずと思って購入しました。しかし味が独特すぎて、個人的に合いませんでした。商品説明には飲みやすいと書いてあるけど、この味は人を選ぶと思います。これなら薬の味を感じずに飲める錠剤の方が良いかも。